すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
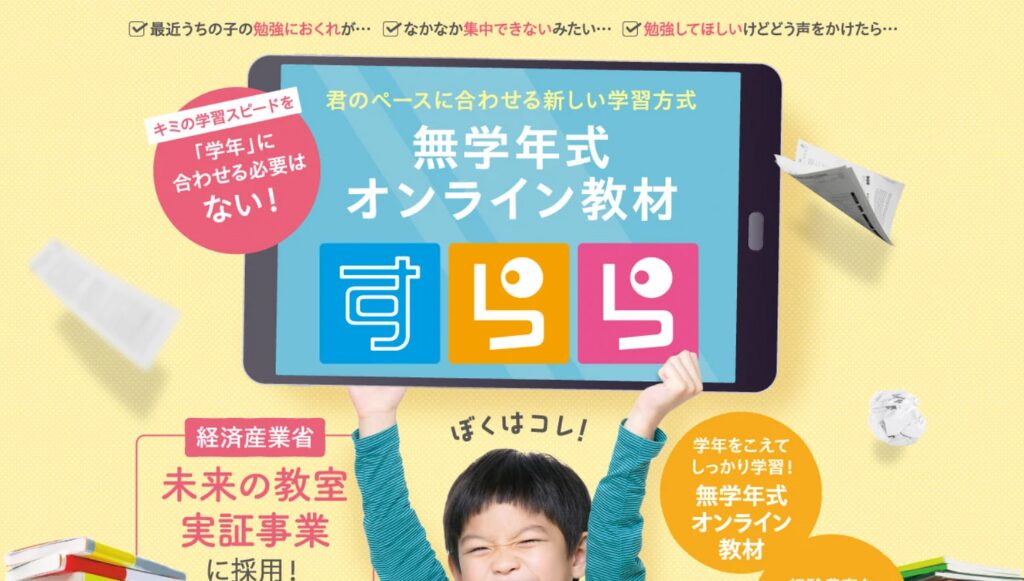
すららは、不登校のお子さんにとって「出席扱い」として認められる可能性があるオンライン学習教材です。
文部科学省の方針により、オンライン学習や自宅学習を「学校教育の一環」として認めるケースが増えており、すららでの学習内容や進捗状況を学校に提出することで、出席扱いになる可能性があります。
すららは、AIによる個別指導や無学年式カリキュラムを採用しており、学習の質とサポート体制が整っているため、学校側からも学習内容が認められやすいのが特徴です。
また、すららコーチによる個別指導や定期的なフィードバックもあるため、学校に通わなくても質の高い教育を受けられる環境が整っています。
この記事では、すららが「出席扱い」として認定される理由について詳しく解説します。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、学習内容の質が高く、進捗状況や成果が正確に記録されるため、学校側から「正式な学習」として認められやすいのが特徴です。
不登校のお子さんが自宅で学習をしている場合、「本当に学習が進んでいるのか」「内容が適切なのか」といった不安を学校側が感じることがあります。
しかし、すららではAIが学習内容や理解度を自動で分析し、詳細なデータを記録してくれるため、客観的な証拠として学校に提出しやすくなっています。
このように、学習の質や進捗を証明できることが、出席扱いとして認められやすい理由となっています。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、日々の学習記録や理解度、進捗状況を自動的にデータ化してくれるため、これを「学習記録レポート」として学校側に提出することが可能です。
このレポートには、どの教科をどれだけ学習したか、どの程度理解が進んでいるかが詳細に記録されており、学校側が「実際に学習が行われている」ということを客観的に判断できる材料となります。
このような客観的な証拠があることで、学校側も安心して「出席扱い」として認めやすくなっています。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
すららでは、学習状況が自動的に記録・可視化されるため、保護者が手動で進捗を管理したり、データをまとめたりする必要がありません。
AIが自動でデータを収集し、進捗レポートを作成してくれるため、保護者の負担が大幅に軽減されます。
また、このデータを学校側に提出することで、「どのくらい学習が進んでいるか」が明確になるため、学校側も「しっかりと学習が行われている」という安心感を得ることができます。
このように、学習状況が客観的に可視化されることが、出席扱いとして認められる大きなポイントとなります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららでは、すららコーチによる個別対応が行われているため、学習計画がしっかり立てられ、無理なく継続的に学習を進めることが可能です。
不登校のお子さんの場合、「自分のペースで学習を進めたい」「わからないところをじっくり復習したい」といったニーズがありますが、すららでは個別対応によりこれらのニーズに柔軟に対応しています。
また、継続的なサポートがあることで、学習が途切れることなくスムーズに進むため、学校側からも「学習が安定している」と評価されやすくなっています。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららでは、すららコーチが個別に学習計画を立て、進捗を管理してくれます。
学習内容や理解度を把握した上で、適切なタイミングで復習や新しい単元への移行を提案してくれるため、計画的に学習を進めることが可能です。
また、つまずいた場合にはコーチがすぐに対応してくれるため、学習が途切れることなく安定したペースで取り組むことができます。
このように、計画的かつ継続的に学習が進められていることを学校側にアピールできるため、出席扱いとして認められやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
すららコーチは、学習状況を把握した上で、個別にカスタマイズされた学習計画を作成してくれます。
学習の進捗状況を見ながら計画を随時調整し、無理なく理解を深められるようサポートしてくれるため、自然と「できた」という成功体験を積み重ねることができます。
このように、コーチのサポートがあることで「計画性」と「継続性」が維持されていることを学校側に説明できるため、出席扱いとして認められやすくなります。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららは無学年式を採用しているため、お子さんの理解度に合わせて自由に学年を行き来しながら学習を進めることが可能です。
理解が追いついていない場合には基礎に戻って復習し、得意な分野はどんどん先に進めることができるため、ストレスなく学習を進めることができます。
また、無理に学校の進度に合わせる必要がないため、お子さん自身のペースで安心して取り組めます。
この柔軟性が、学校側から「無理なく学習が進んでいる」と評価され、出席扱いとして認められる要因になっています。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららは、家庭・学校・すららの三者が連携して学習を進められる仕組みが整っています。
不登校のお子さんの場合、「自宅で学習している状況」を学校側に正しく伝えることが重要になりますが、すららではそのサポートが充実しています。
すららの専任コーチが学習内容や進捗状況をまとめたレポートを作成し、これを学校側に提出することで「学習がきちんと行われている」ことを証明することができます。
また、家庭側での負担を最小限に抑えながら、学校とすららがスムーズに連携できるため、不登校の状況でも安心して学習を進めることができるのが特徴です。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
すららでは、学校に「出席扱い」として認められるために必要な書類や手続きについて、専任コーチが具体的に案内してくれます。
たとえば、「学習記録レポート」や「進捗状況報告書」など、学校が必要とする書類をどのように準備すればよいのかを丁寧に教えてくれるため、保護者が手探りで進める必要がありません。
さらに、必要に応じてフォーマットのテンプレートを提供してくれるため、効率的に書類を作成できるのがポイントです。
これにより、学校側に対して正確なデータを提出できるため、出席扱いとして認定されやすくなります。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららの専任コーチは、学習内容や進捗をまとめた「学習レポート」の作成をサポートしてくれます。
レポートのフォーマットもすらら側で用意してくれるため、保護者がゼロから作成する必要はありません。
また、提出前には内容を確認し、必要に応じて修正やアドバイスも行ってくれるため、学校側に正確で説得力のあるデータを提出することが可能です。
これにより、「この生徒はきちんと学習している」と学校側に安心してもらえるため、出席扱いとして認められやすくなります。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
すららでは、担任や校長とスムーズに連絡を取れるようにするためのサポートも行っています。
学校との連携が取れていないと「自宅学習がどの程度進んでいるのか」が学校側に伝わらず、出席扱いとして認めてもらえないことがあります。
すららの専任コーチが保護者や学校との橋渡し役となり、必要に応じて「学校側との連絡のタイミング」や「話し合いの場の持ち方」などをアドバイスしてくれます。
これにより、学校側との信頼関係が築きやすくなり、出席扱いの認定がスムーズに進む可能性が高まります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省が公式に認定した「不登校対応教材」としての実績があります。
文部科学省は、不登校のお子さんに対して「オンライン学習」や「自宅学習」を教育活動の一環として認める方向性を打ち出しており、すららはその方針に基づいた教材として位置づけられています。
このため、すららでの学習を出席扱いと認める学校や自治体が増えてきています。
また、全国の教育委員会や学校と連携した導入実績があるため、学校側からも「信頼できる教材」として受け入れられやすいのが特徴です。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国の教育委員会や学校と積極的に連携しており、実際に多くの学校で「不登校支援教材」として導入されています。
すららの無学年式カリキュラムやAIによる個別対応、すららコーチのサポート体制が学校側から高く評価されており、「学校教育に十分対応できる内容」として受け入れられています。
また、教育委員会との連携により、すららを利用した学習記録が「正式な教育活動」として認められるケースも増えてきています。
こうした実績があるため、学校側も「すららでの学習を出席扱いにする」ことへの抵抗感が少なくなっています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文部科学省が推奨する「不登校支援教材」として公式に認められており、実際に多くの自治体や学校で採用されています。
特に、不登校のお子さんに対して「学習の遅れを取り戻す」「自信を持って学校に復帰できる」ことを目的に、すららが活用されている事例が増えています。
すららの無学年式カリキュラムやAIサポート、専任コーチによる学習計画の作成などが、学校側から「効果的な学習支援」として高く評価されています。
このため、すららを利用していることで「学習がきちんと進んでいる」と判断されやすく、結果的に出席扱いとして認められるケースが多くなっています。
すららは「ただのオンライン教材」ではなく、「不登校支援」「学習遅れのフォロー」「成功体験の積み重ね」など、学校教育と同等の価値を提供しているため、学校側も出席扱いとして認定しやすくなっているのがポイントです。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、自宅での学習環境が「学校での学習」と同等レベルであると認められやすいことが、出席扱いになる大きな理由の一つです。
不登校のお子さんが出席扱いとして認められるためには、家庭での学習が「学校教育と同等レベルの質」であることが求められます。
すららは、学習内容が文部科学省の学習指導要領に準拠しているだけでなく、理解度に応じたフィードバックや評価システムがしっかりと整備されているため、学校教育に準ずる環境を自宅で実現できるのが特徴です。
これにより、学校側から「実際に教育活動が行われている」と判断されやすくなり、出席扱いとして認定されやすくなっています。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららで提供されている学習内容は、すべて文部科学省が定める「学習指導要領」に基づいて作成されています。
そのため、学校で扱われている教科書の内容や単元と一致していることが多く、「学校での授業」と同等の学習効果が期待できます。
また、学校の進度に合わせて無学年式で柔軟に対応できるため、「学校の授業内容をカバーできている」という安心感を学校側が持ちやすくなっています。
たとえば、小学校から中学校にかけての国語、算数(数学)、理科、社会、英語といった主要教科はもちろん、応用的な問題や実践的な知識まで幅広く対応しています。
また、学校の授業進度に合わせて「わからない部分に戻る」「得意な部分を先取りする」といった柔軟な対応も可能です。
このように、学校での学習内容に準拠しているため、「すららでの学習が学校教育と同等である」と学校側に認められやすくなっています。
さらに、すららでは単なる「知識のインプット」にとどまらず、「問題を解く→理解度を確認する→必要に応じて復習する」という一連の学習サイクルが組み込まれています。
このため、「すららで学習している=学校教育と同等の効果がある」と学校側が判断しやすくなっています。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、AIを活用した「学習の評価」と「フィードバック」のシステムが整っています。
お子さんが問題を解いた後、AIが即座に採点を行い、間違えた箇所については「どこが間違っているのか」「どうすれば正解できるのか」を詳しくフィードバックしてくれます。
このように「理解度→確認→修正」というプロセスが自動化されているため、単に問題を解くだけでなく、しっかりと理解を深めることができるのが特徴です。
また、すららコーチが学習の進捗を定期的にチェックし、「この部分の理解が不十分なので復習が必要」といった具体的なアドバイスを提供してくれます。
AIによる自動的なフィードバックと、すららコーチによる人的なサポートが組み合わさることで、学習の質が担保され、「学校教育と同等の環境が整っている」と学校側に認められやすくなっています。
たとえば、AIによるフィードバックで「算数の文章題が苦手」と判定された場合には、すららコーチが「どの単元に戻るべきか」「どのように復習を進めるべきか」といった具体的なプランを提案してくれます。
また、フィードバック内容が「学習記録」として自動的に保存されるため、「どの部分でつまずいたか」「どの程度理解が進んでいるか」を学校側に提出することも可能です。
さらに、すららでは「達成度」や「学習スコア」が可視化されるため、「どの程度理解が進んでいるか」を客観的に証明することができます。
これにより、学校側も「学習がきちんと進んでいる」ということを容易に確認できるため、出席扱いとして認められやすくなります。
すららの評価システムには「正解率」「達成度」「繰り返し学習の回数」など、学習効果を示すデータが細かく記録されています。
これらのデータを「学習記録レポート」として学校に提出できるため、「学校教育と同等レベルの学習が行われている」と学校側に納得してもらえる可能性が高まります。
このように、すららは「教育の質」と「学習の証拠」が両立しているため、出席扱いとして認定されやすくなっているのです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららは、不登校の子どもが自宅で学習を続けることができるオンライン学習サービスです。
不登校の理由や状況によっては、すららを利用していることで「出席扱い」として認められる可能性があります。
出席扱いになるためには、学校や教育委員会への申請が必要となります。
この制度を活用することで、学校に通えない期間も学習を継続しやすくなるため、不登校の子どもにとって大きな助けとなります。
ここでは、すららを活用して出席扱いにするための具体的な申請方法について詳しく説明していきます。
申請方法1・担任・学校に相談する
すららを利用して出席扱いにしてもらうためには、まず学校側との相談が必要です。
担任の先生や学校の担当者に、すららを利用して学習を継続していることを伝え、出席扱いになるための手続きについて確認します。
学校によって対応が異なる場合があるため、具体的な要件や申請に必要な書類をしっかりと確認しておくことが大切です。
また、担任の先生が制度に詳しくない場合は、校長先生や教育委員会に相談してみるのもよいでしょう。
学校側にすららを活用した学習の効果や取り組みの様子を理解してもらうことで、スムーズに話が進みやすくなります。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校によっては、出席扱いの申請に必要な書類や条件が異なることがあります。
一般的には、すららを利用して学習をしていることを示す学習記録やレポートの提出が求められることがあります。
また、出席扱いに関する教育委員会の指針や校内規定があるかどうかも確認しておくことが重要です。
必要な書類や条件が明確になったら、早めに準備を進めておくことで、手続きがスムーズに進みます。
特に、学習状況や成果を記録しておくことで、学校側にすららを利用した学習が効果的であることを示しやすくなります。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由や状況によっては、医師の診断書や意見書が求められるケースもあります。
医師の診断書が必要な場合は、早めに準備を始めることで手続きがスムーズになります。
また、学校や教育委員会によって診断書の内容に求められる条件が異なることがあるため、あらかじめ内容を確認しておくことが大切です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
不登校の理由が「病気」や「精神的な不調」である場合、診断書の提出が必要になることがあります。
特に、精神的な理由で不登校となっているケースでは、学校側が状況を正確に理解するために医師の診断書や意見書が求められることが多いです。
診断書が必要かどうかは学校や教育委員会に事前に確認しておくことが重要です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
医師の診断書や意見書を用意する場合、精神科や心療内科、小児科で作成してもらうことが一般的です。
診断書には「不登校の状態」と「学習を継続することが望ましい」といった内容を記載してもらう必要があります。
医師にすららを活用した学習の状況や、不登校の理由を正確に伝えることで、診断書の内容が具体的になり、学校側も判断しやすくなります。
また、診断書の提出期限や提出方法についても事前に確認しておくと安心です。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららを利用して出席扱いにしてもらうためには、学習記録を学校に提出する必要があります。
すららには学習進捗を確認できる機能があり、それを活用して「どの教科をどれだけ学習したか」「どの程度理解できているか」といった情報をレポートとしてまとめることができます。
学校側にとっても、具体的な学習状況を把握できるため、出席扱いとして認められる可能性が高くなります。
学校によって必要な書類や記録内容が異なる場合があるため、担任の先生や学校の担当者に事前に確認しておくとスムーズに進められます。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららには、学習の進捗状況をレポートとして出力できる機能があります。
これをダウンロードして、担任の先生または校長先生に提出します。
レポートには「学習時間」「達成度」「理解度」などが具体的に記録されており、学校側が出席扱いを判断する際の重要な資料となります。
提出する際には、すららでの学習がどのように役立っているか、子どもが学習に取り組む姿勢や努力の様子も合わせて伝えると、学校側の理解が深まります。
また、学校の求めるフォーマットや記入事項がある場合は、それに従って準備を進めましょう。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いを申請するためには、学校指定の「出席扱い申請書」を作成する必要があります。
この申請書には、すららを利用していることや、どのような学習成果があるかを記載します。
また、出席扱いが認められることで、学習がどのように継続されるかについても説明を加えると良いでしょう。
申請書の記入は子ども本人が行う場合もありますが、保護者がしっかりとサポートしてあげることで、スムーズに作成できます。
記載内容に不備がないかを事前に確認しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いの申請は、学校や教育委員会の承認を受けることで正式に認められます。
学校によっては、学校長の判断のみで出席扱いが決定するケースもあれば、教育委員会への申請が必要になるケースもあります。
申請書や学習記録を提出した後は、学校側の対応を確認し、必要に応じてフォローアップを行いましょう。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
学校側の手続きとしては、提出した申請書や学習記録をもとに校長先生が判断を行います。
校長先生が「すららでの学習が継続されており、教育的効果がある」と判断した場合、出席扱いが認められる可能性が高くなります。
校長先生に理解してもらうためには、すららを使った具体的な学習状況や成果をしっかりと伝えることが大切です。
また、学校側の対応が遅れている場合は、担任の先生や学校の窓口に相談して、進捗状況を確認すると良いでしょう。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
学校側の判断だけでなく、教育委員会の承認が必要になるケースもあります。
その場合、学校が教育委員会への手続きを進めるため、保護者や本人が直接やり取りを行う必要はあまりありません。
ただし、必要な書類や補足事項を求められることもあるため、学校側と密に連携して対応することが大切です。
教育委員会が出席扱いを判断する際には、学習記録や医師の診断書などが重要な資料となるため、漏れなく提出するようにしましょう。
手続きに時間がかかることもあるため、早めに準備を始めておくと安心です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
すららを利用して不登校でも出席扱いになることには、さまざまなメリットがあります。
出席扱いとして認められることで、学習の遅れや内申点への影響を減らすことができるだけでなく、子どもの自己肯定感を維持したり、進学の選択肢を広げたりする効果も期待できます。
また、親としても「学校に行かせなければ」というプレッシャーが軽減されることで、精神的な負担が軽くなる可能性があります。
ここでは、すららを活用して出席扱いになることの具体的なメリットについて詳しく見ていきます。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
すららを利用して出席扱いになることで、学校に出席しているとみなされるため、内申点が大きく下がるリスクを減らせます。
特に中学や高校では、出席日数が内申点に大きく影響することが多いため、出席扱いになることで進学への影響を最小限に抑えられます。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
不登校の状態が続くと、欠席日数が増えてしまい、内申点への影響が避けられません。
しかし、すららを活用して出席扱いとなれば、欠席扱いの日数を減らすことができるため、結果的に内申点が下がるリスクを軽減できます。
学校側がすららを通じた学習状況や成果を評価してくれれば、学習意欲や取り組み姿勢もプラスに評価される可能性があります。
その結果、学校の成績や進学に関する評価が安定しやすくなります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
進学の際に重要になるのが、成績や内申点です。
すららを活用して出席扱いとなれば、出席日数が不足していることで受験資格を失ったり、成績が不利になるといったリスクを避けられます。
特に中学や高校では、出席日数や内申点が合否に直結することが多いため、出席扱いが認められることで進路の選択肢が広がります。
また、すららを利用していることで「学習への積極的な取り組み」が評価され、志望校へのアピール材料になることもあります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校の期間が長くなると、授業の進度に追いつけなくなることへの不安を抱える子どもが多くいます。
すららを活用すれば、自宅で自分のペースで学習を進められるため、授業の遅れを気にせずに安心して取り組めます。
また、継続的に学習することで、学力を維持できるだけでなく、自己肯定感の低下も防ぐことができます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららでは、自分の理解度に合わせて学習内容を進めることができるため、授業の進度に遅れることなく、必要な学習を補うことができます。
わからない部分があっても、繰り返し学習できる機能や個別指導のサポートがあるため、学校の授業よりも自分のペースで理解を深められます。
また、すららでの学習を通じて「自分でもできる」という成功体験を積むことで、学習に対する自信も取り戻しやすくなります。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
不登校の状態が続くと、「学校に行けない自分はダメだ」と自己肯定感が低下してしまうことがあります。
しかし、すららを活用して学習を継続することで「できることがある」「頑張っている自分がいる」という自信につながります。
また、すららの進捗レポートで学習成果が目に見えることで、達成感や自己効力感を感じやすくなり、ポジティブな気持ちを維持しやすくなります。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを持つ親にとって、「学校に行かせなければ」というプレッシャーや「学習が遅れてしまう」という不安は大きなストレスになります。
すららを活用して学習が継続でき、出席扱いが認められることで、親としての精神的な負担が軽減されます。
また、学校やすららのサポートを受けることで、子どもに対して過度なプレッシャーを与えることなく、安心して見守ることができるようになります。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららには「すららコーチ」と呼ばれる学習サポーターがいるため、親がすべてをサポートする必要はありません。
学校の担任や校長先生と連携しながら、すららコーチと一緒に子どもの学習をサポートできるため、親が1人で悩みを抱えることなく、協力体制を築くことができます。
また、学校や教育委員会とも連携しながら進めることで、手続きや申請がスムーズに進む可能性が高くなります。
このように、すららを通じたサポート体制が整うことで、親としての負担が大きく減り、子どもとの関係も安定しやすくなります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを利用して出席扱いを認めてもらうためには、いくつかの重要な注意点があります。
すららが文部科学省のガイドラインに基づいた教材であることを学校側にしっかりと説明し、理解を得ることが必要です。
また、不登校の理由によっては医師の診断書や意見書が求められることもあるため、早めに準備を進めておくことが大切です。
出席扱いの申請は学校側の協力が不可欠なため、準備不足や誤解が生じないよう、事前にしっかりと確認しておくことが成功へのポイントになります。
ここでは、すららを活用して出席扱いを認めてもらうために押さえておきたい注意点について詳しく解説します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららを利用して出席扱いにしてもらうためには、学校側の理解と協力が欠かせません。
学校の担当者や担任の先生がすららについて十分に理解していない場合、手続きがスムーズに進まないことがあります。
そのため、すららが文部科学省のガイドラインに基づいている教材であることを明確に説明し、学校側に納得してもらうことが重要です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは文部科学省の「出席扱いの要件」を満たしている教材です。
そのため、学校側に「すららが文科省のガイドラインに準拠している」ことを丁寧に説明することが重要です。
すららは「ICT教材」として認められており、教育効果があることが実証されているため、学校側も理解しやすくなります。
すららの公式サイトやパンフレットなどを活用して、学校側に具体的な情報を提示すると、より信頼してもらいやすくなります。
また、学校側に誤解が生じないように「すららでどのように学習しているか」「どのようなサポートを受けているか」を正確に伝えることが大切です。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
学校側に理解してもらうためには、すららの学習内容や成果を示す資料を準備しておくと効果的です。
すららの進捗レポートや学習状況を示すデータを印刷して持参すると、学校側がより具体的に理解しやすくなります。
また、担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生にも早めに相談しておくことで、学校全体での理解と協力が得やすくなります。
特に、校長先生の承認が必要なケースが多いため、担任の先生を通じて校長先生に働きかけてもらうとスムーズに進みやすくなります。
学校側との話し合いでは、「すららを利用することで学習効果が得られていること」や「学習継続の意欲があること」をしっかりと伝えることがポイントです。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由や状況によっては、医師の診断書や意見書の提出が必要になることがあります。
特に、不登校の理由が「体調不良」や「精神的な不調」である場合、学校側が状況を正確に理解するために医師の診断書や意見書を求めるケースが多くなります。
早めに医師に相談し、必要な書類を準備しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合、学校側が出席扱いとして認定するには医師の診断書が必要になるケースが多いです。
医師の診断書に「すららを通じて学習を継続できていること」「学習を通じて子どもに前向きな変化があること」が明記されていると、学校側も判断しやすくなります。
診断書を依頼する際は、子どもの学習状況や精神的な状態を詳しく説明しておくことが大切です。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書が必要な場合は、早めに通院している小児科や心療内科に相談しましょう。
医師に「出席扱いを申請するための診断書が必要」であることを伝えれば、対応してもらいやすくなります。
また、医師によっては診断書のフォーマットが決まっている場合もあるため、学校側に確認しておくとスムーズです。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
医師に診断書を依頼する際には、家庭学習の状況や学習への意欲を具体的に説明しましょう。
「すららを利用してどれだけ学習しているか」「学習に対して前向きな姿勢が見られるか」を伝えることで、医師も診断書にポジティブな内容を書きやすくなります。
医師の診断書に「すららでの学習が効果的であり、学習意欲がある」といった内容が含まれていると、学校側が出席扱いとして認めやすくなります。
また、医師に診断書を依頼する際は、提出期限や記載事項を事前に確認しておくことが大切です。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
すららを利用して出席扱いを認めてもらうためには、学習時間や学習内容が「学校に準ずるレベル」である必要があります。
単なる自習や家庭学習ではなく、「学校の授業に相当する学習」をしていると認められることが重要です。
学習内容が学校のカリキュラムと一致しているか、学習時間が学校の授業時間に近いかどうかを学校側が確認するケースが多いため、意識して準備を進めましょう。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
出席扱いにするためには、「すららを使った学習」が学校の授業に準じた内容である必要があります。
ただの自習や参考書を使った勉強では、出席扱いとして認められないケースが多いため、すららのカリキュラムが「学校教育の指針に沿っている」ことを学校側にしっかり説明することが重要です。
すららは文部科学省のガイドラインに準拠した教材であるため、その点を具体的に伝えることで、学校側の理解が得やすくなります。
また、すららの教材を活用していることを証明するために、学習記録や進捗レポートを提出すると効果的です。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いとして認められるためには、学習時間が「学校の授業時間に近い」ことも重要なポイントです。
一般的には1日2〜3時間程度の学習が目安とされているため、学校側に提出する学習レポートに「毎日一定の学習時間を確保している」ことを明記すると良いでしょう。
また、学習時間が不規則になりすぎると、学校側が「安定した学習が行われている」と判断しにくくなるため、できるだけ学習スケジュールを固定し、学校の授業時間に近い時間帯で学習を進めることを意識しましょう。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
主要教科(国語・数学・英語など)だけでなく、理科・社会・音楽・美術・体育などの副教科もバランスよく学習することが求められる場合があります。
すららでは主要教科を中心に学習できますが、音楽や体育などの教科は別の方法で補完する必要があるかもしれません。
学校側に確認して、「主要教科だけでなく、副教科の取り組みも出席扱いとして認められるかどうか」を相談しておくと安心です。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いの条件として「学校との定期的なコミュニケーション」を求められるケースがあります。
学習状況を学校と共有し、進捗を報告することで、学校側も出席扱いとして認めやすくなります。
また、学校側が学習状況を正しく把握できるようにすることで、安心して出席扱いを判断してもらえる可能性が高まります。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学校側が「すららでの学習を出席扱いにするかどうか」を判断するためには、学校側に定期的に学習状況を報告することが必要です。
すららで学習していることや、学習の進捗が順調であることを学校側に具体的に伝えることで、学校側も出席扱いとして判断しやすくなります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららには学習状況をまとめた「学習レポート」をダウンロードできる機能があります。
このレポートを月に1回程度、担任の先生や校長先生に提出すると良いでしょう。
学習レポートには「学習時間」「達成度」「理解度」などが記載されているため、学校側に「きちんと学習している」ことをアピールできます。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、学習状況を確認するために「家庭訪問」や「面談」を求められることがあります。
このような対応に前向きに協力することで、学校側が安心して出席扱いとして判断しやすくなります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
担任の先生とメールや電話で定期的に連絡を取り、すららでの学習状況を共有することも大切です。
学校側との信頼関係を築くことで、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
また、学校側からの質問や不安にすぐに対応することで、円滑に手続きを進めることができます。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
出席扱いにするために、教育委員会への申請が必要になるケースもあります。
教育委員会によっては、すららでの学習内容や成果に関する資料を求められることがあるため、早めに準備しておくと安心です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会に提出する資料として、すららの学習レポートや医師の診断書などが必要になることがあります。
学校と相談しながら「どのような資料を準備すれば良いか」「提出期限はいつか」などを確認しておくことが大切です。
教育委員会とのやり取りは学校側が代行してくれるケースが多いですが、必要に応じて保護者も説明やサポートを求められることがあります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを利用して出席扱いを認めてもらうためには、いくつかの成功ポイントを押さえておくことが大切です。
学校によっては、すららを使った学習に対する理解や認識が異なるため、適切なアピールや準備を行うことで、学校側が前向きに対応してくれる可能性が高くなります。
ここでは、すららで出席扱いを認めてもらうために効果的なポイントを具体的に紹介していきます。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
すららで出席扱いになった「他の学校の成功事例」を学校に紹介することは非常に効果的です。
学校側が「他校でも認められている」という前例を知ることで、「すららを利用した学習が出席扱いになる」という安心感につながります。
また、学校側が出席扱いの判断に迷った場合も、「他校の前例がある」という事実があることで、承認しやすくなる可能性があります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
すららは文部科学省のガイドラインに沿った教材であり、全国の学校で出席扱いとして認められている実績があります。
他の学校で「すららを使った学習が出席扱いとして認められた」事例を紹介することで、学校側もすららに対して安心感を持ちやすくなります。
実際に他校で出席扱いになったケースを具体的に説明し、「すららを活用した学習が教育効果を持っている」ことを理解してもらうことが重要です。
事例を紹介する際には、「どのような取り組みをしたか」「どのように効果があったか」などの詳細な内容を伝えると、学校側も判断しやすくなります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトには、実際に出席扱いとして認められた学校や事例が紹介されています。
この情報をプリントアウトして持参すると、学校側にとっても説得力が増します。
「他校で実際に認められている」という事実は、学校側が出席扱いを判断する際の重要な材料になります。
すららの公式サイトにある具体的な成功例や学習効果に関するデータを学校側に見せることで、安心感を持ってもらいやすくなります。
特に「教育委員会の承認を得ているケース」や「校長先生が出席扱いとして判断したケース」など、具体的な成功例を示すと効果的です。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
すららを使った学習が出席扱いとして認められるためには、学校側に「本人が学習に前向きに取り組んでいる」ことを理解してもらうことが大切です。
学校側に「すららを通じて学習意欲が高まっている」という事実が伝わることで、出席扱いを承認してもらえる可能性が高まります。
特に、本人が自分自身の言葉で「頑張っていること」や「すららを通じて感じていること」を伝えることで、学校側の印象が良くなりやすくなります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
学校側に「すららでの学習を出席扱いとして認めてほしい」と伝える際に、本人が書いた「学習の感想」や「目標」を提出すると効果的です。
たとえば、「すららを使って数学が分かるようになった」「英語のテストで点数が上がった」などの具体的な成果や、「もっと頑張りたい」「高校に進学したい」といった前向きな目標が書かれていると、学校側も「本人が真剣に取り組んでいる」と認識しやすくなります。
本人が自分の言葉で書いたものは、説得力があるため、担任の先生や校長先生に良い印象を与える可能性が高くなります。
また、具体的な成果やエピソードを交えることで、本人の努力や取り組み姿勢が伝わりやすくなります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校側が出席扱いを判断する際に、本人との面談を求められるケースがあります。
その場合、本人が積極的に参加して「すららを通じて学習を頑張っていること」を自分の言葉で伝えることが重要です。
「すららを使ってどの教科が得意になったか」「学習を通じて自信がついたこと」などを具体的に話すことで、学校側に「学習に取り組む姿勢」が伝わりやすくなります。
また、親や担任の先生がフォローしつつ、本人が主体的に話すことで「やる気」が伝わりやすくなります。
学校側も「本人が自分の意思で取り組んでいる」という点を重視するため、積極的な姿勢を見せることで好印象を与えることができます。
面談の際には、親や担任の先生からも「すららを使った学習状況」や「本人の努力や成果」を補足することで、より説得力を増すことができます。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
すららを利用して出席扱いを認めてもらうためには、無理のない学習計画を立てることが非常に重要です。
短期間で結果を出そうと焦ってしまうと、途中で学習が続かなくなったり、学習への意欲が低下してしまうことがあります。
出席扱いになるためには「学習を継続していること」が大きなポイントとなるため、本人に合った無理のない学習スケジュールを作ることが必要です。
特に、不登校の状態にある場合、精神的な負担や体調の波があることも考慮しながら、現実的な学習ペースを設定することが求められます。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
出席扱いを認めてもらうためには、「学習が継続していること」が重要なポイントとなります。
そのためには、無理をしすぎず、本人に合ったペースで取り組める計画を立てる必要があります。
すららは、自分の理解度や進度に合わせて学習を進められるため、柔軟にスケジュールを調整することが可能です。
無理な計画を立ててしまうと、途中で学習に対するモチベーションが下がったり、体調を崩してしまうリスクがあります。
そのため、1日あたりの学習時間を「短め」に設定しても、毎日継続することが重要です。
たとえば、「1日30分からスタートして、慣れてきたら1時間に増やす」など、段階的に負担を増やしていくことで、無理なく学習を継続しやすくなります。
また、学校側には「継続的に取り組める計画を立てていること」を示すことで、出席扱いとして判断してもらいやすくなります。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららには「すららコーチ」と呼ばれる専門のサポートが用意されています。
すららコーチは、本人の学習状況や理解度を把握しながら、無理なく続けられるスケジュールを一緒に立ててくれる存在です。
たとえば、「学校の時間割に合わせてスケジュールを作る」「苦手な教科は短時間からスタートして徐々に増やす」といった柔軟な対応が可能です。
また、学習の進捗状況や理解度をすららコーチが把握しているため、学習が遅れている場合はペースを調整してもらえることも大きなメリットです。
本人の状態ややる気に合わせて細かく調整しながら、無理なく続けられる計画を作ることで、長期的に安定した学習が可能になります。
すららコーチと定期的に相談しながらスケジュールを見直すことで、出席扱いを認めてもらうための重要な条件である「継続性」を確保しやすくなります。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、「すららコーチ」のサポートを最大限に活用することが重要です。
すららコーチは、学習の進め方やペースの調整だけでなく、学校に提出するためのレポート作成や、学習証明のサポートも行ってくれます。
本人が学習に集中しやすい環境を作るためにも、すららコーチとの連携を強めることが成功のポイントとなります。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
出席扱いを申請する際に必要になる「学習レポート」や「学習証明書」は、すららコーチが作成のサポートをしてくれます。
すららには学習状況を記録する機能が備わっており、進捗データや理解度をまとめたレポートを作成することが可能です。
すららコーチは、このデータをもとに学校に提出できる形式にまとめる手助けをしてくれます。
たとえば、「1週間に何時間勉強したか」「どの教科を重点的に学習したか」「テストや確認問題の結果がどうだったか」といったデータを含めることで、学校側が出席扱いとして判断しやすくなります。
また、学校側から「もう少し具体的なデータを出してほしい」「教科ごとの進捗を細かく知りたい」といった要望があった場合も、すららコーチが柔軟に対応してくれます。
さらに、学習の進捗に問題があった場合には、すららコーチが「どこでつまずいているか」を分析し、学習計画を見直すアドバイスをしてくれます。
すららコーチのサポートがあることで、学習の継続がしやすくなるだけでなく、学校側にも「しっかり学習が行われている」ことをアピールしやすくなるため、出席扱いとして認められる可能性が高くなります。
すららコーチとの連携を強化することで、本人が無理なく継続できる環境を整えることができます。
学校側からの信頼を得るためにも、すららコーチと相談しながら、具体的なデータや成果を学校に伝えることが重要です。
すららコーチの存在は、出席扱いを成功させるための強い味方になるため、積極的にサポートを受けながら学習を進めていくことが成功の鍵となります。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした/でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた/時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり/イライラして何度も怒ってしまっていましたが、
すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました/完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり/タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました/キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした/教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました/他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららは不登校の子どもでも出席扱いになる可能性があるオンライン教材として、多くの家庭で利用されています。
そのため、利用者からさまざまな質問や疑問が寄せられることがあります。
ここでは、すららに関してよくある質問について詳しく解説します。
すららをこれから利用しようと考えている方や、すでに利用中で疑問を感じている方にとって役立つ情報をまとめています。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すららはうざい」という口コミがある理由として、主に「キャラクターの声が合わない」「繰り返しの演習が多い」「ペースが合わない」などが挙げられます。
すららはAIを活用して個々の学習進度に合わせた内容を提示してくれますが、人によっては「説明が長い」「繰り返しがしつこい」と感じてしまうことがあるようです。
特に、キャラクターが話す内容や声のトーンが合わないと感じる場合、「集中できない」「イライラする」といった意見が見られます。
また、すららは理解度に応じて何度も復習を行うスタイルのため、「同じことを繰り返すのが面倒」と感じる子どももいるようです。
とはいえ、繰り返し学習は記憶の定着に効果的であり、理解不足を補うために重要なプロセスでもあります。
そのため、「うざい」と感じる原因が「繰り返し」や「キャラクターの声」にある場合は、すららの設定を変更したり、学習時間を短く調整したりすることで解決できることもあります。
どうしてもキャラクターが合わない場合は、音声をオフにしてテキストベースで学習する方法もあるため、自分に合ったスタイルを見つけることで快適に利用できる可能性があります。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには発達障害を持つ子ども向けの「発達障害コース」が用意されています。
このコースは、通常のすららコースと同じくAIが個々の理解度や進度に合わせたカリキュラムを提示してくれるだけでなく、発達障害特有の「苦手な部分」や「つまずきやすいポイント」に対応したサポートが組み込まれています。
発達障害コースの料金プランは、月額制で契約することが基本となっており、具体的な料金は利用する教科数やサポート内容によって異なります。
通常のコースと同じ料金体系であることが多いですが、発達障害コースには専門の「すららコーチ」が付いているため、個別指導やカウンセリングなどのサポートを受けられる点が特徴です。
すららコーチが学習スケジュールの調整やモチベーションの維持をサポートしてくれるため、発達障害を持つ子どもでも無理なく継続しやすくなっています。
料金の詳細は公式サイトに掲載されているため、最新の情報を確認したうえで申し込むことをおすすめします。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららを利用したタブレット学習は、不登校の子どもでも出席扱いになる可能性があります。
文部科学省のガイドラインでは、ICT(情報通信技術)を活用した学習が出席扱いとして認められる条件が示されています。
すららはこのガイドラインに準拠した教材であり、学校側が「すららでの学習を教育的効果がある」と判断すれば、出席扱いとして認められる可能性が高くなります。
実際にすららを使って出席扱いになったケースもあり、学習記録や進捗レポートを学校側に提出することで、出席扱いの判断材料として利用されることがあります。
ただし、学校によって対応が異なるため、担任の先生や校長先生に「すららを使って出席扱いになるかどうか」を事前に相談しておくことが大切です。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、定期的にキャンペーンを実施しており、キャンペーンコードを利用すると月額料金が割引になることがあります。
キャンペーンコードは、申し込みページで入力することで適用されます。
具体的には、公式サイトの申し込み画面にある「キャンペーンコード入力欄」にコードを入力し、「適用」ボタンを押すことで割引が反映されます。
キャンペーン内容によっては「初月無料」や「月額料金○%オフ」などの特典が適用されることがあります。
キャンペーンコードには使用期限や条件が設定されている場合があるため、申し込み前に詳細を確認しておくことが大切です。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会する場合は、公式サイトの「マイページ」から手続きが可能です。
マイページにログインした後、「契約管理」または「アカウント管理」の項目から「退会手続き」を選択し、画面の指示に従って進めます。
退会手続きを完了すると、すららの利用が停止され、次回の課金も停止されます。
ただし、契約期間の途中で退会手続きを行った場合、日割りでの返金は行われないため、契約期間が満了するタイミングで退会手続きを進めることをおすすめします。
また、退会後はすららでの学習データが消去されることがあるため、必要なデータは退会前に保存しておくと安心です。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的に入会金と毎月の受講料以外に追加で料金が発生することはありません。
ただし、利用するデバイス(タブレットやパソコン)の購入やインターネット環境の整備に関しては、別途費用がかかる場合があります。
すらら自体の受講料は、契約するコースや対象学年によって異なりますが、一度契約すれば、契約期間内において追加の教材費や特別な講座料金が発生することはありません。
すららの受講料には、「教材費」「システム利用料」「すららコーチによるサポート料」が含まれているため、安心して利用することができます。
ただし、特別なキャンペーンやプラン変更時には追加費用が発生するケースがあるため、申し込み前に契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。
また、クレジットカード決済や銀行振込など、支払い方法によっては手数料が発生することがあるため、支払い方法もあわせて確認しておくと良いでしょう。
契約更新時やプラン変更時には料金が変更になる可能性もあるため、すららの公式サイトで最新情報を確認しておくと安心です。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、1つの契約で兄弟が一緒に利用することはできません。
すららのアカウントは、受講者1人ごとに契約が必要となっており、1つのアカウントを兄弟で共有することはシステム上できない仕組みになっています。
すららはAIによる個別最適化学習を提供しており、受講者それぞれの理解度や進度に応じてカリキュラムが組まれるため、1つのアカウントを複数人で使用すると、学習データが混在してしまい、正確な学習プランが作成できなくなる恐れがあります。
そのため、兄弟それぞれに個別の契約を結ぶ必要があります。
ただし、すららには「兄弟割引」や「家族割引」といった割引制度があるため、兄弟で利用する場合はこれらの制度を活用するとお得に利用できる可能性があります。
兄弟で受講する場合は、公式サイトやサポートセンターで割引制度の詳細を確認し、最適なプランを選ぶと良いでしょう。
また、兄弟で受講する場合、それぞれに「すららコーチ」がつき、個別の学習サポートを受けることができるため、兄弟それぞれに最適化された学習プランを進められる点も大きなメリットです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには英語も含まれています。
小学生コースでは「国語」「算数」「理科」「社会」「英語」の5教科に対応しており、英語は文法や単語だけでなく「リスニング」や「スピーキング」といった総合的な英語力を育成できる内容になっています。
特に、すららの英語教材は「読む・聞く・話す・書く」の4技能をバランスよく習得できるように設計されているため、小学生の段階から英語を体系的に学べることが特徴です。
英語の学習では、AIが受講者の理解度に応じて出題レベルや内容を調整してくれるため、無理なく自分のペースで学習を進めることができます。
また、発音練習やリスニングの強化を目的としたトレーニング機能も備わっているため、単なる暗記だけでなく、実践的な英語力を身につけることができます。
すららの英語教材は「学校の教科書」に準拠しているため、学校で学ぶ内容とリンクしている点も安心できるポイントです。
さらに、すららコーチが「発音チェック」や「リスニング対策」など、個別のアドバイスを行ってくれるため、苦手なポイントを克服しやすくなります。
小学生から英語に慣れ親しむことで、中学・高校での英語学習にもスムーズに対応できるようになります。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの最大の特徴のひとつが「すららコーチ」によるサポート体制です。
すららコーチは、受講者一人ひとりの学習状況を把握しながら、適切なアドバイスや学習計画の見直しを行ってくれます。
すららコーチのサポート内容は、「学習の進捗管理」「理解度チェック」「苦手分野の強化」「モチベーション維持」など多岐にわたります。
受講者が学習につまずいた場合、すららコーチがつまずきの原因を分析し、「どの単元を復習するべきか」「理解が足りていない箇所をどう補うか」など、具体的なアドバイスを提供してくれます。
また、学習の進捗が順調に進んでいる場合でも、さらなる理解を深めるための応用問題やチャレンジ課題を提案してくれるため、学習レベルを着実に向上させることが可能です。
さらに、すららコーチは保護者とも定期的に連絡を取り、学習の進捗状況や今後の課題について相談に応じてくれます。
必要に応じて学習計画の見直しや学習内容の調整を行うことで、受講者にとって最適な学習環境を維持できるようにサポートしてくれます。
学校での学習進度に合わせたカリキュラム調整や、学校側に提出する学習レポートの作成もサポートしてくれるため、出席扱いを申請する際にも心強い存在となります。
すららコーチとの連携を強化することで、受講者が自信を持って学習に取り組むことができる環境が整います。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
すららは、不登校の生徒が在宅で学習を続けるための有効なサポートとなる可能性があります。
文部科学省の定める「出席扱い」の制度を利用すれば、すららでの学習が学校の出席と認められるケースがあります。
ただし、出席扱いを受けるためには学校への申請が必要であり、学校側の判断やサポート体制に依存する部分もあります。
制度を利用する際には、学校との連携をしっかりと行い、必要な書類や手続きについて事前に確認しておくことが重要です。
自分に合った学習スタイルを見つけ、安心して学びを続けていける環境を整えることが大切です。