【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
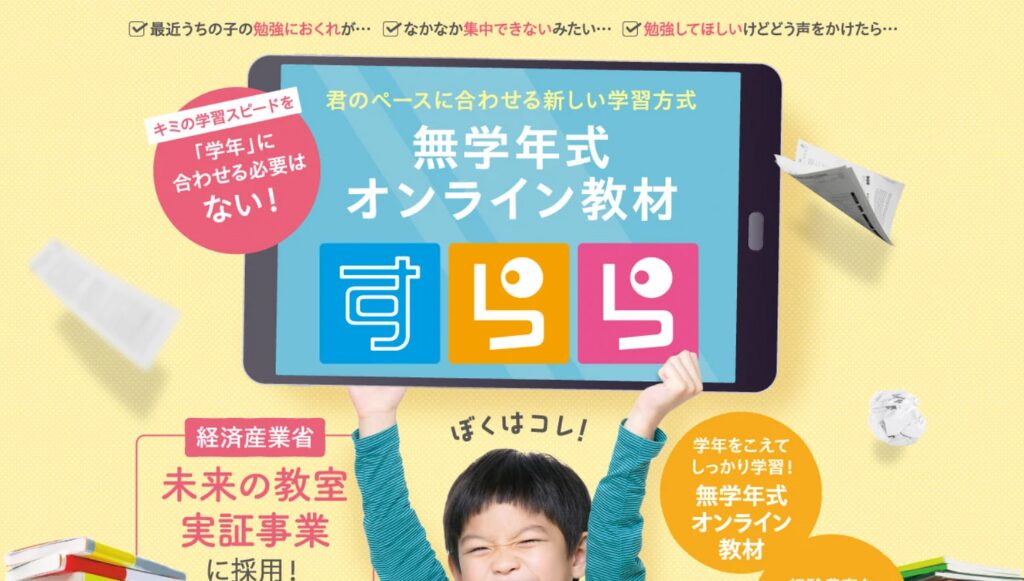
すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
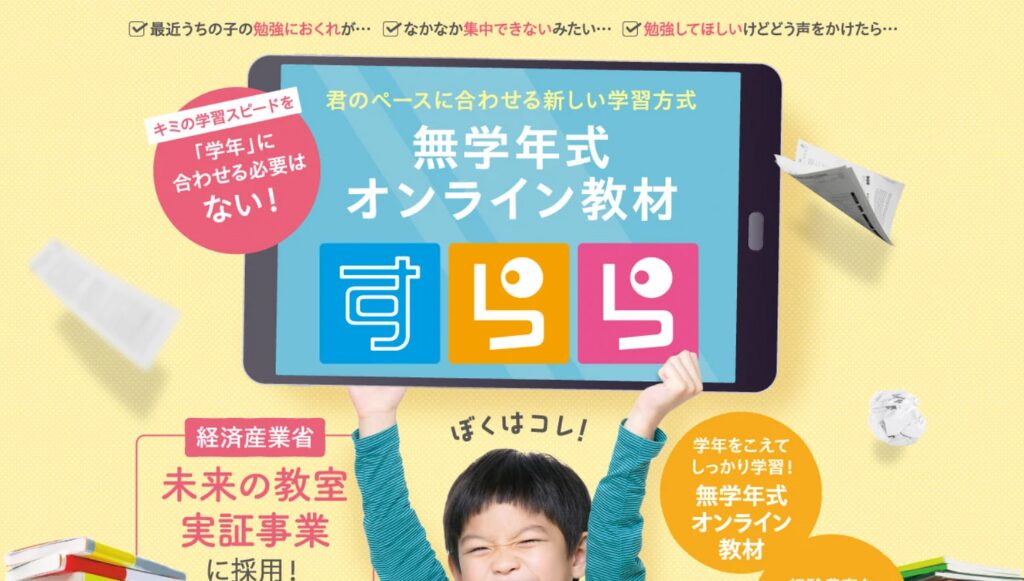
「すらら」は、無学年式のオンライン学習教材として注目されています。
「すらら うざい」というネガティブな印象を持っている人もいますが、実際には「自分のペースで学習できる」「わかりやすい授業スタイル」「子どもがやる気を出しやすい」といった多くのメリットがあります。
特に「無学年式」や「対話型アニメーション授業」といった独自のシステムが人気の理由となっており、子どもが学習を続けやすい工夫が随所に取り入れられています。
「すらら」は、インターネット環境があればPC・タブレット・スマホなどから利用可能で、学校の授業内容に対応しているため「予習・復習・先取り」が自在に行えるのが特徴です。
ここでは、すららが選ばれるおすすめのポイントについて詳しく紹介します。
すららのおすすめポイントをまとめました
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
「すらら」の最大の特徴は「無学年式」であることです。
一般的な学習教材は「学年」に応じたカリキュラムが組まれているため、学校の進度に沿って進めなければなりませんが、「すらら」は学年に関係なく「理解できるところから始める」「わからなければ戻る」という柔軟な学習が可能です。
たとえば、算数や数学で「小学校高学年の内容が理解できていない」という場合でも、「すらら」では小学校低学年の単元に戻ってやり直すことが可能です。
逆に、理解が早く「もっと進みたい」という場合には、中学内容や高校内容まで先取りして学ぶことも可能です。
この「無学年式」のシステムによって、「得意な教科はどんどん進める」「苦手な教科は理解できるまで戻ってやり直す」といった柔軟な学習が可能になります。
学校の進度に関係なく、自分の理解度や学習ペースに応じた「最適なレベル」で学べるため、学習のストレスが軽減されます。
また、子どもの理解度に合わせた「個別指導」が可能なため、学校の授業についていけない場合や、逆に物足りない場合でも「すらら」を使えば、自分に合ったレベルで学習を続けることができるのが大きなメリットです。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
「すらら」のもうひとつの大きな特徴は「対話型アニメーション授業」です。
多くのオンライン学習教材は「動画を視聴するだけ」の一方通行の授業形式ですが、「すらら」ではアニメキャラクターが「先生役」となって、子どもと「対話」しながら授業が進みます。
たとえば、算数の授業で「分数の計算」がテーマの場合、キャラクターが「これはどう思う?」「どこがわからないかな?」と問いかけながら授業が進行します。
子どもが考えたり、答えたりすることで「能動的な学習」ができる仕組みになっています。
「キャラクターが説明する」→「子どもが考える」→「キャラクターがフィードバックをする」という流れが自然に作られているため、集中力が続きやすく、理解度も高まります。
また、「キャラクターがわかりやすく褒めてくれる」ことで、子どものモチベーションが自然と上がる仕組みになっています。
難しい単元でも「図」や「アニメーション」を活用して説明されるため、「イメージ」として理解しやすく、視覚的に「わかった!」という感覚を得やすくなります。
たとえば、「直角三角形の面積」を説明する際に、「三角形を並べて正方形を作る」→「その半分が面積」というように「図解」を使って視覚的に解説されるため、理解が深まりやすくなります。
また、間違えた場合でも「どこでつまずいたのか」をアニメーションキャラクターがわかりやすく指摘してくれるため、「なぜ間違えたのか」を自然に振り返ることができます。
「ここで間違えたんだね」「次はこうしてみよう」といった具体的なアドバイスがあることで、ただ「解き直す」だけでなく「理解し直す」ことができるのがポイントです。
さらに、「学習達成度」が可視化されるため、「できた!」という達成感が得やすくなります。
1単元を終えるごとに「クリア!」といった表示が出たり、ポイントが加算されたりするため、ゲーム感覚で楽しみながら学習を続けることができます。
「視覚」「聴覚」「感覚」をフル活用した「対話型授業」だからこそ、理解度が高まりやすく、飽きずに続けられるのが「すらら」の魅力です。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
「すらら」は「子どもが続けやすい」ことも大きな特徴です。
授業の中でキャラクターが「よくできたね!」「素晴らしい!」と褒めてくれるため、子どもが「やる気」を維持しやすくなります。
また、問題に正解すると「ポイント」が加算されたり、ステージが進んだりするため、「達成感」や「モチベーション」が自然とアップします。
勉強が苦手な子どもでも、「キャラクターが褒めてくれるからやる気が出る」「ポイントが貯まると次のレベルに進める」といった仕組みがあることで、「勉強が楽しい!」という感覚を持つことができます。
これにより、「勉強=つまらない・難しい」というイメージがなくなり、自発的に取り組む姿勢が身につきます。
「すらら」は、「無学年式」で自由に進めることができるため、子どもが「自分のペース」で「楽しく」学習を進められる環境が整っています。
これこそが、「すらら」が選ばれる理由です。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
「すらら」の大きな魅力のひとつに「すららコーチ」の存在があります。
「すららコーチ」は、専門知識を持つプロの学習指導者で、子どもひとりひとりに合わせた「学習計画の作成」や「進捗管理」「学習サポート」を担当してくれます。
これにより、親が細かく学習を管理しなくても、子どもが自分のペースで学習を続けられる環境が整っています。
「すららコーチ」は、子どもの「得意」「苦手」「目標」「希望」をもとに「オーダーメイドの学習計画」を立ててくれるため、「何をどこまで進めればよいのか」「どの単元を復習すればよいのか」といった疑問がなくなります。
これにより、子どもは「やるべきこと」が明確になり、親が口を出さなくてもスムーズに学習を進めることができます。
たとえば、「算数が得意で国語が苦手な子」の場合、コーチが「算数はどんどん進めて、国語は基本からじっくり復習」といった柔軟な学習計画を立ててくれます。
また、学習進度や理解度に応じて、計画を適宜修正してくれるため、「無理なく」「効率的に」学習を進めることが可能です。
「すららコーチ」によるサポートは、単なる「学習計画の作成」だけにとどまりません。
学習中に「つまずき」があった場合、「すららコーチ」に直接質問や相談ができるため、「わからないまま放置される」ということがなくなります。
たとえば、「この問題が解けない」「この単元が理解できない」といった場合でも、「すららコーチ」が適切なアドバイスをしてくれるため、学習が止まることがありません。
また、親に対しても「進捗状況」や「理解度」がわかるように定期的な報告があるため、「どの単元が理解できているか」「どの部分が苦手か」を親が把握することができます。
これにより、「子どもがきちんと学習できているかどうか」が目に見えてわかるため、親も安心して見守ることができます。
「すららコーチ」の存在によって、「親が細かく指示を出す必要がない」「学習進度や理解度を見守るだけでよい」という環境が整うため、親の負担が大きく軽減されます。
忙しい家庭や共働き家庭でも、子どもが自発的に学習を進められる仕組みができるため、「すらら」は多くの家庭で選ばれています。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
「すらら」は、発達障害や不登校の子どもにも対応できるように設計されており、「どの子にもやさしい学習環境」を提供しています。
実際に「すらら」はその取り組みが評価され、文部科学大臣賞を受賞しています。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子どもにとって、「すらら」が適している理由は、「個別対応」と「わかりやすい授業構成」にあります。
たとえば、「集中力が続かない」「すぐに飽きてしまう」といった特徴がある場合でも、「短い動画授業」「図やアニメーションを使った視覚的な解説」「テンポのよい授業進行」によって、無理なく学習を続けることができます。
「すらら」は無学年式であるため、「自分に合ったレベル」から学習をスタートできるのも大きなメリットです。
たとえば、小学5年生の子どもが「小学2年生レベルの算数からやり直したい」という場合でも、「すらら」では自由に戻って復習することが可能です。
「理解できるまで戻る→できたら進む」というサイクルが自然に作られているため、子どものペースで無理なく学習を進められます。
また、不登校の子どもにとっても「すらら」は有効です。
学校に通えないことで「授業内容に追いつけない」「学習習慣が崩れてしまった」といったケースでも、「すらら」は自宅で自分のペースで学習できるため、学力の維持・向上につながります。
さらに、「つまずき」への対応も万全です。
「すらら」にはAIによる「理解度解析機能」があり、「どの部分で理解不足があるか」を自動で解析してくれます。
その結果に基づいて「類似問題」や「理解不足を補うための問題」を自動で提示してくれるため、効率的に弱点を克服することができます。
たとえば、「分数の計算」が苦手な場合、AIが「分数の計算問題」を重点的に出題し、理解度を高めることができます。
また、「理解度」が高まったと判断されれば、AIが「次のレベル」に自動で進めてくれるため、自然な流れでスムーズに先に進むことができます。
「すらら」は、発達障害や不登校に対応した「やさしい設計」になっているため、「学校の授業についていけない」「学習習慣が定着しない」「学習に対して苦手意識がある」といった子どもでも無理なく取り組むことができます。
「すらら」は「対話型アニメーション授業」や「無学年式の柔軟な学習システム」といった基本的な特長に加え、「AIによる理解度解析」「すららコーチによる個別指導」といった手厚いサポート体制が整っているため、「どの子にも寄り添った学習」が可能です。
この「学びやすい環境」があるからこそ、「すらら」は発達障害や不登校に悩む家庭からも高い評価を受けています。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
「すらら」の大きな強みのひとつが「オンラインテスト」と「リアルタイム学力分析」です。
単に動画を視聴して理解しただけでは、実際に「定着しているかどうか」を確認することは難しいですが、「すらら」では「オンラインテスト」と「AIによる定着度診断」によって、学習成果がしっかり可視化されます。
これにより、「どこまで理解できているか」「どの部分が苦手か」「次に何を学ぶべきか」が明確になります。
オンラインテストは、授業を受けた直後に実施されることが多く、理解した内容をすぐに確認できる仕組みになっています。
たとえば、「分数の足し算」の授業を受けた後に、その場で「分数の計算問題」が出題されることで、「理解したつもり」ではなく「本当に理解できているか」をチェックできます。
間違えた場合でも、AIが「どこでつまずいたか」「何が理解できていないか」を自動解析し、その内容をもとに「個別の対策問題」を自動生成してくれます。
これにより、「間違えたまま放置される」ということがなく、「つまずき」を即座に解消できる仕組みになっています。
たとえば、「分数の通分」が苦手だと判断された場合、AIが「通分の練習問題」を重点的に出題してくれます。
また、同じ問題を解いたときに正解できるようになるまで、適切なレベルで反復練習を行わせることで、理解度が確実に高まります。
さらに、「すらら」では定期的に「定着度診断テスト」も実施されています。
このテストによって、「その時点でどの単元が理解できているか」「どの単元が苦手か」をAIが分析し、学習カリキュラムに反映してくれます。
学習状況や理解度は、保護者にも「レポート」として自動配信されます。
これにより、「子どもが何をどこまで理解しているか」「どの部分が苦手なのか」を親がリアルタイムで把握できるため、親が「どうサポートすればよいか」が明確になります。
たとえば、「算数は得意だけど国語が苦手」といった場合には、親が「国語に重点を置いたサポート」を行うことができるようになります。
また、学習レポートは「グラフ」や「スコア」として視覚的に表示されるため、子ども自身が「どれだけ成長したか」を実感しやすくなっています。
「やれば成果が出る」という実感が「やる気」につながるため、学習のモチベーションアップにも効果的です。
「オンラインテスト」と「リアルタイム学力分析」によって、「理解度チェック」「苦手克服」「成果確認」のサイクルが自然とできあがるため、確実に成績アップが期待できます。
「学習成果が目に見える」という成功体験が、子どもの自信につながり、さらに「勉強が楽しい」と感じるようになります。
この「好循環」が、成績向上に直結しています。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
「すらら」の英語学習は、「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能をバランスよく鍛えられるのが特徴です。
英語は「単語や文法を理解しているだけ」では不十分で、「聞く」「読む」「話す」といった総合的な力を身につけることが重要ですが、「すらら」ではその3技能を効果的に習得できるカリキュラムが用意されています。
リスニング力を鍛えるために、「すらら」ではネイティブスピーカーによる音声を活用しています。
授業中に「単語」「フレーズ」「会話」の音声をネイティブスピーカーが発音してくれるため、「自然な発音」や「英語のリズム」に慣れることができます。
また、リスニング問題の中には「音を聞き取って答える」タイプの問題もあり、リスニング力を強化できます。
たとえば、「What is this?」といった質問に対して「It’s an apple.」と答えるような基本的なリスニング問題から、「長文を聞いて内容を理解する」といった応用的な問題まで、段階的に取り組める構成になっています。
スピーキングに関しては、「音読チェック機能」が搭載されています。
発音をAIが解析してくれるため、「どこが正しく発音できているか」「どこが間違っているか」を即座にチェックしてくれます。
これにより、「自分の発音が正しいかどうか」を確認しながら、自然な発音を身につけることができます。
たとえば、「This is a pen.」と発音した際に、「This」の発音が不明瞭だった場合、AIが「Th」の発音を強化するためのフィードバックをしてくれます。
このように、「どの部分を修正すればよいか」が具体的にわかるため、効率よくスピーキング力を強化できます。
リーディングに関しては、英単語や英文法が「アニメーション」で視覚的に解説されるため、理解がしやすくなっています。
単なる「丸暗記」ではなく、「イメージ」として文法や構造を理解できるため、自然と「文章が読める」ようになります。
たとえば、「疑問文」や「否定文」の文構造をキャラクターがアニメーションで示してくれることで、「どこをどう直せば正しい文になるのか」が視覚的に理解できます。
このように、視覚・聴覚・発話を組み合わせた学習により、「英語が自然と身につく」仕組みが整っています。
「すらら」の英語学習は「インプット」と「アウトプット」のバランスが非常に良く、英検対策や中学受験対策にも効果的です。
「聞く」「話す」「読む」がバランスよく鍛えられることで、自然と「使える英語」が身につきます。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
家庭でオンライン学習を利用するとき、料金体系が「1人分じゃない」というのはとても大きなメリットです。
一般的なオンライン教材は、1人あたりに月額料金がかかることが多いため、兄弟や姉妹がいる家庭では費用がかさんでしまうことがあります。
その点、このサービスでは1つの契約で兄弟や姉妹が一緒に利用できるため、家計に優しい料金プランになっています。
さらに、科目を自由に追加できるので、必要な学習内容に絞って無駄なく利用できるのが魅力です。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
このサービスでは、1つの契約で兄弟や姉妹が同時に利用できるため、追加料金がかかりません。
例えば、小学生の兄と中学生の妹がいる家庭でも、別々に契約する必要がなく、1つのアカウントで同時に学習が可能です。
それぞれが自分に合ったレベルの教材を使えるので、年齢や学年が違っても無理なく学習を進められるのがポイントです。
家計の負担を減らしつつ、効果的に学習できるのが嬉しいところです。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
小学生と中学生がいる家庭では、学年や学習内容が異なるため、通常はそれぞれ別の教材を用意しなければなりません。
しかし、このサービスでは同じ契約内で学年や学習レベルに合わせた教材を利用できるため、コストパフォーマンスが非常に良いです。
兄は算数や理科、妹は英語や社会など、それぞれが必要な科目を自由に選んで学べるので、無駄がなく、効率的に学習を進めることができます。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
必要な科目だけを自由に選んで追加できるのも大きなメリットです。
例えば、国語や数学だけを重点的に学習したい場合、その2科目だけを選択して契約できます。
また、途中で「理科も追加したい」と思ったときには、簡単に追加可能です。
必要な科目だけに絞れるため、無駄な費用がかからず、学習の効率もアップします。
柔軟な料金体系が、家庭にとっても負担を減らすポイントです。
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
「すらら」は家庭用タブレット教材として注目を集めていますが、ネット上では「うざい」という声も見かけることがあります。
とはいえ、実際には他の教材にはないメリットが多く、特に学習サポートや不登校・発達障害対応など、他の教材にはない独自の強みを持っています。
ここでは、「すらら」の代表的なメリットを詳しく見ていきます。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
「すらら」の大きな特徴のひとつが、プロの学習コーチによるサポート体制です。
一般的なタブレット教材は基本的に自学自習が中心ですが、「すらら」ではプロのコーチが個別にサポートしてくれるため、子どものやる気や理解度をしっかり引き出してくれます。
自宅学習でも孤独を感じることなく、継続しやすい環境を作ってくれるのがポイントです。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
「すらら」では、専属のコーチが学習の進捗をしっかり管理してくれます。
どこが理解できていて、どこでつまずいているのかを細かく把握してくれるため、子どもがつまずいているポイントを的確にサポートしてくれます。
また、コーチが適切なアドバイスをしてくれるため、理解不足をそのままにすることがなく、効果的な学習が可能です。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
子どもの学習ペースや理解度に合わせて、コーチが個別にスケジュールを作成してくれるのも「すらら」の大きな魅力です。
特に苦手科目に対しては重点的なスケジュールを組んでもらえるため、効果的に苦手克服が可能です。
無理なく続けられるスケジュールを提案してくれるため、子どもがストレスを感じることなく学習を続けられるのがポイントです。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
「すらら」は、不登校や発達障害の子どもへの対応にも特化しています。
一般的なタブレット教材ではカバーしきれない、個別のニーズに対応したカリキュラムやサポートが用意されているため、安心して学習を進めることができます。
特に、不登校や発達障害の子どもに対して理解が深く、無理なく続けられる工夫がされています。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
「すらら」は文部科学省からも認められた実績があり、不登校や発達障害の子どもに対応した教材として採用されています。
そのため、学校や教育機関からも信頼されており、安心して取り組むことができます。
実際に「すらら」を導入している学校も増えており、教育現場でもその効果が認められています。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
「すらら」を使用して学習を進めている場合、出席扱いになる学校が多いのもメリットのひとつです。
自宅での学習が学校の授業と同等に評価されるため、無理に登校しなくても、学習状況が認められるのは大きな安心材料になります。
不登校の子どもでも、学校の進度に遅れることなく学習を続けられるため、本人の自信にもつながります。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
「すらら」は発達障害に特化したサポート体制も整っています。
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠陥多動症)、LD(学習障害)などの特性に合わせたカリキュラムが組まれているため、それぞれの子どもに合った学習方法で取り組めます。
また、理解しやすい動画やイラストを多用した教材が用意されているため、子どもの特性に合わせた無理のない学習が可能です。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
「すらら」では、学年に縛られない「無学年学習」が可能です。
通常の学習教材は学年に合わせてカリキュラムが組まれていますが、「すらら」では子どもの理解度や進度に応じて自由にさかのぼったり、先取りしたりできるため、無理なく学習を続けられます。
理解が難しい単元はじっくり取り組み、得意な分野はどんどん先に進めるため、効率的な学習が可能です。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
「すらら」の無学年学習では、学年を気にせずに自由に単元を選ぶことができます。
苦手な単元があれば基礎に戻って理解を深め、得意な科目はどんどん先に進めることができるため、子ども自身のペースで学習を進められます。
これにより、苦手分野を克服しつつ、得意な分野をさらに伸ばせるのが大きな魅力です。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達障害の子どもにとって、「つまずいたまま進まない」という状況は大きなストレスになります。
「すらら」では、理解できていない箇所をそのままにせず、個別に戻って理解を深めることができるため、無理なく自分のペースで学習を進められます。
AIやコーチが理解不足を見逃さず、サポートしてくれるので、つまずきを一つずつ解消できるのが強みです。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
「すらら」では、AIによる学習診断と人間のコーチによるサポートを組み合わせたWサポート体制が整っています。
AIが子どもの学習状況を詳細に分析し、その結果をもとにコーチが学習計画を調整してくれるため、効果的な学習設計が可能です。
AIだけでは対応しきれない個別の理解度やつまずきも、人間のコーチがきめ細かくフォローしてくれるため、着実に成果が出ます。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
AIによる客観的なデータ分析と、人間コーチによる感覚的なサポートが組み合わさることで、効果的な学習が実現します。
AIが「苦手分野」や「理解の浅い部分」を正確に把握し、それに対してコーチが適切な学習スケジュールを組んでくれるため、子どもが無理なく学習を進められるのがポイントです。
このWサポート体制は、他のタブレット教材にはない「すらら」ならではの強みです。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
AIはデータに基づいた客観的なサポートが得意ですが、子ども一人ひとりの性格や理解度の変化までは完全に把握できません。
「すらら」では、AIが分析したデータをもとにコーチが子どもに合った対応をしてくれるため、無理なく学習を進められます。
例えば、学習スピードが遅れている場合はスケジュールを調整し、理解度が向上してきたらスピードアップするといった対応が可能です。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
「すらら」では、デジタル教材でありながら記述力を鍛えられるカリキュラムが用意されています。
通常、タブレット学習では「選択問題」が多くなりがちですが、「すらら」では「論理的に書く力」や「説明する力」を重視した問題も多く含まれています。
読解力や思考力を深めることで、単なる暗記ではなく、実践的な学力が身につきます。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
「すらら」では、記述問題に重点を置いたカリキュラムが用意されています。
問題を単に解くだけではなく、自分の言葉で説明することを求められるため、論理的思考力や表現力が鍛えられます。
また、解答内容に対してコーチが具体的なアドバイスをくれるため、正確に「伝える力」が身につきます。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
デジタル教材でありながら、読解力と記述力の両方を強化できるのは「すらら」ならではの特徴です。
タブレット上で直接文章を書いたり、説明したりすることで、国語力や論理的思考力が鍛えられます。
また、コーチが記述内容を細かくチェックしてくれるため、表現力や文法力の向上にもつながります。
このようなトレーニングができる教材は珍しく、「すらら」ならではの強みです。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
「すらら」は、途中でやめた場合でもスムーズに再開できるのが大きな特徴です。
子どもによっては、体調や精神的なコンディションの変化で学習を一時的に中断することがありますが、「すらら」ではそのような場合でも簡単に復帰できる仕組みが整っています。
進捗データが保存されているため、どこからでも再開できるのがポイントです。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
「すらら」では、学習データがクラウドに保存されているため、途中で中断しても再開がスムーズです。
例えば、体調不良や家庭の事情で数週間学習を休んだ場合でも、次にログインしたときに進捗データがそのまま残っているため、再開時に迷うことがありません。
途中でやめても、ストレスなく学習を再開できるので、無理なく続けられるのがポイントです。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
不登校や発達障害の子どもにとって、学習ペースに波があるのは自然なことです。
体調や気分によって集中力が続かないこともありますが、「すらら」なら自由に休むことができ、再開もスムーズに行えるため、無理なく自分のペースで取り組むことができます。
決まったペースで進める必要がないため、子ども自身の調子に合わせて柔軟に対応できるのが「すらら」の強みです。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
「すらら」は、不登校支援教材として教育機関からも高く評価されています。
実際に「すらら」を活用している子どもが「出席扱い」として認定されるケースも多く、学校や教育委員会との連携実績も豊富です。
これにより、学校に通えない期間でも、家庭学習が正式に評価されるため、保護者や子どもにとっても大きな安心材料となっています。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
「すらら」で学習を続けていることで、学校が「出席扱い」として認めるケースが多くあります。
文部科学省が「すらら」を推奨していることもあり、学校側も公式な教材として評価しているため、出席日数にカウントされることが増えています。
自宅学習でも学校と同等の評価を得られるため、保護者にとっても大きな安心材料になります。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
「すらら」は、不登校支援教材として学校や医療機関との連携実績も豊富です。
例えば、医療機関でのカウンセリングを受けながら「すらら」を使った学習が取り入れられているケースもあります。
また、学校側と連携して学習計画を調整していることもあり、学校に行かなくても学習の進度が認められるなど、安心して続けられる環境が整っています。
【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
「すらら」は多くのメリットがある一方で、ユーザーから「うざい」と感じられることがあるのも事実です。
どんなに優れた教材でも、すべての子どもにぴったり合うわけではありません。
特に、学習スタイルや性格によっては「すらら」が合わないと感じることがあります。
ここでは、実際に「うざい」と言われる原因やデメリットについて詳しく解説します。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
「すらら」では、コーチが定期的にサポートや進捗確認の連絡をしてくれますが、これが逆に「しつこい」と感じるケースもあるようです。
学習が順調に進んでいるときや、自分のペースで進めたい子どもにとっては、頻繁な連絡がプレッシャーになったり、煩わしく感じたりすることがあります。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
「すららコーチ」のサポートは、手厚くて丁寧ですが、自分で計画を立てて学習したいタイプの子どもには合わないことがあります。
自分のペースで進めたいのに、進捗確認やアドバイスが頻繁に届くことで「干渉されている」と感じることもあります。
特に、放っておいてほしいタイプの子どもにとってはストレスになる可能性があります。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
「すらら」はAIが学習状況を分析し、自動で学習計画を立ててくれるため、効率的に学習を進められる反面、「やらされている」という感覚が強くなる場合があります。
計画通りに進まないと「遅れている」と感じてしまい、それがストレスにつながることがあります。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
AIが自動的に学習計画を作成してくれるのは便利ですが、「このスケジュール通りにやらなければならない」と感じてしまう子どももいます。
理解が追いつかないときや、体調が優れないときでも計画が進んでしまうため、「ついていけない」「サボっている」と感じてしまうケースがあります。
この「縛られている感覚」がプレッシャーになることもあるようです。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
「すらら」は、子どもが親しみやすいようにキャラクターを使ったナビゲーションやアニメーションが取り入れられていますが、これが「子どもっぽい」「くどい」と感じることがあります。
特に高学年や思春期の子どもにとっては、「幼稚っぽい」と思われてしまうことがあるようです。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
小学校低学年や未就学児には親しみやすいキャラクターも、高学年や中学生になると「幼稚っぽい」「ダサい」と感じることがあります。
また、キャラクターが話しかけてきたり、励ましたりするのが「余計なお世話」と感じてしまうケースもあるようです。
このように、年齢や成長段階によってはキャラクターの存在が逆効果になることがあります。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
「すらら」は、サポート体制が手厚い分、勧誘や営業が「しつこい」と感じられることがあります。
特に無料体験や資料請求をした後に、定期的な案内やフォローが続くことで「営業が強引だ」と感じるケースもあるようです。
このような印象がSNSなどで拡散されることで、「すららはうざい」といった声につながっていることも考えられます。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
無料体験後や契約前のフォロー連絡が頻繁に行われるため、それを「営業がしつこい」と感じる人がいるようです。
SNSでも「電話が多い」「メールがしつこい」といった投稿が見られることがあります。
子ども自身は気にしていなくても、保護者にとっては「営業色が強い」と感じてしまうことが、マイナスな印象につながっている可能性があります。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
「すらら」は、他のタブレット教材に比べて料金が高めに設定されています。
そのため、実際に効果を感じられなかった場合に「コスパが悪い」と感じるケースがあります。
特に、子どもが自発的に取り組まない場合や、学習成果が目に見えにくい場合には「料金に見合った効果がない」と不満を感じることもあるようです。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
「すらら」はAIやコーチのサポートが充実しているため、基本的には子どもが1人で取り組める設計になっていますが、実際には「親がサポートしないと進まない」と感じるケースもあります。
特に低年齢の場合、自主的に進めるのが難しいことがあり、その結果「期待していたほどの効果がなかった」と感じる保護者もいるようです。
料金が高めなだけに、効果を感じにくいと「損をした」と思ってしまう可能性があります。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
「すらら」は、家庭用タブレット教材の中でも料金がやや高めに設定されています。
そのため、「コスパが悪いのでは?」「高すぎるのでは?」と感じる人も少なくありません。
ただし、AIを活用した個別最適化や、プロのコーチによるサポートなど、他の教材にはない付加価値があるため、その分の料金が反映されていると考えられます。
ここでは、すららの具体的な料金プランについて詳しく解説していきます。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
「すらら」の3教科(国語・数学・英語)コースは、基礎的な学力を重点的に強化したい場合に適したプランです。
1ヶ月あたりの月額料金は約8,800円(税込)となっており、他のタブレット教材に比べるとやや高めです。
ただし、AIによる学習状況の分析や、コーチによる個別サポートが含まれているため、サポートの手厚さを考慮すると妥当な金額とも言えます。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
「すらら」の3教科(国語・数学・英語)コースは、基礎的な学力を重点的に強化したい場合に適したプランです。
1ヶ月あたりの月額料金は約8,800円(税込)となっており、他のタブレット教材に比べるとやや高めです。
ただし、AIによる学習状況の分析や、コーチによる個別サポートが含まれているため、サポートの手厚さを考慮すると妥当な金額とも言えます。
また、「すらら」の3教科コースは、無学年学習に対応しているため、学年を超えて自由にさかのぼりや先取りが可能です。
子どもの理解度に合わせて学習ペースを調整できるので、無駄なく効果的に学習を進められるのがポイントです。
さらに、苦手分野はコーチがサポートしてくれるため、つまずきをそのままにせず克服できる可能性が高まります。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
5教科(国語・数学・理科・社会・英語)を網羅したプランは、より総合的な学力を強化したい家庭に適しています。
月額料金は約10,978円(税込)で、3教科コースに比べて約2,000円程度の追加料金がかかります。
5教科を一度に学べるため、受験対策や学校の定期テスト対策にも役立ちます。
特に理科や社会は、学校の授業だけでは理解が不十分になりがちな分野ですが、「すらら」ではビジュアルやアニメーションを活用した解説があるため、わかりやすく理解を深められるのが特徴です。
また、AIとコーチによるWサポート体制で、学習スケジュールの管理やつまずきのフォローも受けられるため、5教科全体をバランスよく学習できるのがメリットです。
5教科プランも無学年学習に対応しているため、理解が不十分な単元は学年をさかのぼってやり直し、得意な科目はどんどん先に進めることが可能です。
料金はやや高めですが、サポートの手厚さや学習の自由度を考えると、コストパフォーマンスは決して悪くないと言えるでしょう。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
「すらら」は、家庭用タブレット教材の中でも特に勉強効率や効果が高いと言われています。
AIによる学習状況の分析や、個別にカスタマイズされた学習スケジュールが特徴で、短時間で成果を実感できるのがポイントです。
特に3教科コース(国語・数学・英語)は、基礎力の定着から応用力までバランスよく鍛えられるため、多くの家庭で人気のあるプランとなっています。
ここでは、すらら3教科コースの具体的な勉強効果について詳しく紹介します。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
すららの3教科コース(国語・数学・英語)は、基礎から応用まで幅広く対応できるのが特徴です。
AIが子どもの理解度を自動で分析し、それに基づいて最適なカリキュラムを提案してくれるため、つまずきを放置せずに効果的に学習を進めることができます。
また、プロのコーチによるサポートがあるため、理解不足やモチベーションの低下を防ぐことができるのも強みです。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
「すらら」の3教科コースは、AIが自動で学習状況を分析し、子どもの理解度に応じて最適な問題を提示してくれるため、基礎力が早く定着します。
特に「わかったつもり」を防ぐように、理解不足を繰り返し確認しながら進めるため、苦手な部分をしっかり補強できます。
また、動画やアニメーションを活用した解説により、直感的に理解しやすい工夫がされているため、学習スピードが上がります。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
「すらら」では、単に問題を解くだけでなく、「なぜその答えになるのか」を理解させることで、知識の定着を促します。
AIが苦手分野や理解不足を正確に把握し、それをコーチがフォローすることで、「できる→わかる→応用」の流れがスムーズに作られます。
このため、短時間でも効果的に学習を進めることが可能です。
さらに、学習した内容がテストや実生活で役立つように、実践的な問題も多く取り入れられています。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生の場合、内申点に直結する主要3教科(国語・数学・英語)の成績向上はとても重要です。
「すらら」の3教科コースでは、定期テスト対策や受験対策に特化した学習が可能で、実際に「点数が上がった」「内申点が改善した」といった声も多く聞かれます。
また、AIとコーチによるダブルサポートにより、苦手な単元を繰り返し学習できるため、自然と理解度が深まります。
特に英語では、リスニングやスピーキングに対応した問題も含まれているため、単なる文法や読解力だけでなく、実践的なコミュニケーションスキルも身につけることができます。
数学では、応用問題や文章問題も丁寧に解説されているため、「理解できないまま進む」ということがなく、確実に実力をつけることができます。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
「すらら」の4教科コースは、国語・数学・英語に加えて理科または社会を組み合わせたコースです。
理科や社会は暗記が中心になりやすく、苦手意識を持つ子どもも多いですが、「すらら」では映像授業やAIによる個別サポートを活用して、効率的に学習を進めることができます。
単なる暗記にとどまらず、理解を伴った知識として定着しやすいのが特徴です。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
理科や社会は暗記が必要な範囲が広いため、単に学ぶだけでは記憶が定着しにくいことがあります。
しかし、「すらら」では学習後にAIが自動で理解度を分析し、必要に応じて繰り返し学習や確認テストを提案してくれます。
この反復学習により、知識が長期記憶として定着しやすくなります。
また、単なる暗記だけでなく、問題を解くことで理解が深まり、応用力も自然と身につきます。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
「すらら」では、各単元の重要ポイントを明確に示した学習ができるため、短時間で効率的に知識を習得できます。
AIが子どもの理解度をリアルタイムで把握し、必要な部分だけをピンポイントで学習できるため、無駄な時間がありません。
理科や社会は範囲が広く、覚えることが多いため、効率的な学習ができるのは大きなメリットです。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
塾や学校の授業では、どうしても一斉授業になるため、自分の理解度に合わせた学習が難しいことがあります。
しかし「すらら」では、AIが自動で理解度を分析し、子どもに合わせた最適なカリキュラムを提示してくれるため、短時間で効果的に学習が可能です。
テスト前には弱点を集中的に強化できるため、短期間でも得点アップが期待できます。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
「すらら」の5教科コースは、受験や定期テスト対策に最適なコースです。
国語・数学・英語に加えて、理科・社会もカバーしているため、総合的な学力をバランスよく伸ばすことが可能です。
AIとコーチのWサポートにより、全教科の苦手分野を集中的に強化できるため、内申点アップや受験対策に直結します。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結/ 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
中学生にとって、内申点アップには5教科のバランスが重要です。
「すらら」では、全教科をまんべんなくカバーしながら、AIが苦手分野を重点的に補強してくれるため、内申点アップに直結します。
また、定期テスト前には5教科すべての対策を個別に実施できるため、得意分野をさらに伸ばしつつ、苦手分野も克服できます。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ/模試や過去問対策にも応用できる
「すらら」の5教科コースでは、高校受験を見据えた応用問題や過去問対策にも対応しています。
AIが子どもの理解度を正確に把握し、苦手な分野や出題傾向に合わせたカリキュラムを組んでくれるため、模試や過去問への対応力がアップします。
また、コーチが受験戦略や勉強法のアドバイスもしてくれるため、安心して受験に臨むことができます。
勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
「すらら」では、AIが5教科すべての理解度を細かく分析し、最適な学習スケジュールを自動で作成してくれます。
そのため、「何を勉強すればいいかわからない」という状態にならず、常に効率的に学習を進めることができます。
また、苦手な分野は繰り返し学習を提案してくれるため、自然と得点力が上がります。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
「すらら」は、塾や他のタブレット教材と比較して、時間あたりの学習効果が高いと言われています。
AIが無駄のない学習プランを組んでくれるため、短時間で集中的に学習が可能です。
塾の場合は通学時間や待機時間が発生しますが、「すらら」なら自宅でスキマ時間に効率よく勉強できるため、学習効率が非常に高いのが特徴です。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
「すらら」は、発達障害や不登校の子どもにも対応した家庭用タブレット教材として高く評価されています。
学校の授業ではついていけない子や、集団での学習にストレスを感じる子でも、「すらら」なら自分のペースで安心して学習を進めることができます。
AIが個別の理解度やペースに合わせて学習内容を調整してくれるため、無理なく取り組めるのがポイントです。
ここでは、「すらら」が発達障害や不登校の子どもでも安心して使える理由について詳しく説明します。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
「すらら」は無学年方式を採用しているため、学校の進度に縛られることなく、自分の理解度に合わせて自由に学習を進めることができます。
集団授業のように「クラスメイトについていかなきゃ」というプレッシャーがなく、必要に応じてさかのぼり学習や先取り学習が可能です。
そのため、学習に対するストレスが軽減され、無理なく自分のペースで学ぶことができます。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
学校の授業では「みんなに合わせる」ことが求められるため、理解が追いつかないと焦りやストレスを感じることがあります。
しかし「すらら」では、AIが子どもの理解度を細かく把握し、必要に応じて基礎に戻ったり、得意な分野は先に進んだりすることができるため、無理なくマイペースに学べます。
このため、つまずきをそのままにせず、自然に理解が深まります。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
発達障害の特性に合わせた柔軟な使い方ができるのも「すらら」の魅力です。
– ADHD(注意欠陥・多動性障害)タイプの子は、集中できるタイミングが限られるため、やる気があるときに短時間で一気に進めるスタイルが合っています。
「すらら」では、自分のペースで学習できるため、集中できるときに集中的に取り組むことが可能です。
– ASD(自閉スペクトラム症)タイプの子は、毎日決まったルーティンをこなすことが得意です。
「すらら」では、毎日のスケジュールをAIやコーチが提案してくれるため、安心して一定のペースで取り組むことができます。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
「すらら」はタブレット学習なので、対人関係のプレッシャーやストレスを感じることなく、自分のペースで進められます。
学校の授業や塾では、先生やクラスメイトとの人間関係がストレスになることがありますが、「すらら」ではそういった心配が一切ありません。
アニメーションのキャラクターが優しくナビゲートしてくれるため、安心して取り組めます。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
「すらら」では、アニメーションのキャラクターが優しく解説してくれるため、プレッシャーを感じずに学習に集中できます。
間違えたときも「違うよ!」と叱られることはなく、「こうすれば正解になるよ」とポジティブに導いてくれるため、萎縮したり、落ち込んだりすることがありません。
このように、子どものメンタルに配慮した設計になっているため、安心して学習を続けることができます。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
発達障害のある子どもにとって、人とのコミュニケーションは大きな負担になることがあります。
先生やクラスメイトに「どう思われるか」を気にしてしまい、学習に集中できないケースも少なくありません。
「すらら」はタブレット上で1人で学習できるため、コミュニケーションへの不安がなく、リラックスして学習に取り組むことができます。
また、コーチからのサポートもオンラインを通じて行われるため、顔を合わせる必要がなく、気軽に相談できるのもポイントです。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
「すらら」は、発達障害の子どもにも配慮した「ユニバーサルデザイン」を取り入れており、誰でも理解しやすく、つまずきにくい工夫が随所に施されています。
視覚的にわかりやすいアニメーションや、音声によるサポートなど、さまざまな特性に対応した設計が特徴です。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
「すらら」の教材は、文字情報だけでなく、イラストや図解、音声解説などを組み合わせることで、理解しやすい構成になっています。
特に、文章の読み取りが苦手な子どもでも、視覚的に内容を把握しやすいため、学習のつまずきを防ぐ工夫がされています。
また、重要なポイントは繰り返し登場するため、自然と記憶に残りやすいのが特徴です。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
「すらら」は、読字障害(ディスレクシア)やASD(自閉スペクトラム症)など、言葉の理解に時間がかかる子どもに向けた工夫が施されています。
例えば、文章が読みづらい子どもには、イラストや図を活用して直感的に理解できるように配慮されています。
さらに、要点がシンプルにまとめられているため、情報の整理が苦手な子どもでも理解しやすい設計になっています。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
「すらら」は、視覚情報を中心に理解する「視覚優位」の子にも、耳からの情報が得意な「聴覚優位」の子にも対応しています。
イラストやアニメーションに加え、音声での解説が充実しているため、どちらのタイプの子どもでも無理なく学習を進めることができます。
学習の途中で「読む」「聞く」を自由に切り替えられるため、子どもの特性に合わせた最適な方法で取り組めます。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
「すらら」には、音声速度を自由に調整できる機能が搭載されています。
言葉の理解に時間がかかる子どもは音声を「ゆっくり」に設定し、焦らずに学べる環境を整えられます。
一方、理解が早い子どもは音声を「速め」にすることで、学習をテンポよく進めることができます。
このように、個々の特性に合わせた柔軟な対応が可能な点が「すらら」の強みです。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
「すらら」では、学習中に間違えても否定されたり叱られたりすることがなく、安心して挑戦できる環境が整っています。
特に、発達障害の子どもは「失敗」を極端に恐れたり、萎縮したりすることがありますが、「すらら」では「否定」ではなく「納得」を重視した指導が行われるため、子どもの自己肯定感を守りながら学習を進めることができます。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
「すらら」では、間違えた場合に「なぜ間違えたのか」「どの部分が理解できていなかったのか」を丁寧に解説してくれます。
その際も「ダメ!」と突き放すのではなく、「こう考えればよかったんだね」と優しく導いてくれるため、子どもが自信を失うことなく、次の問題に前向きに取り組めるのが特徴です。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
学校や塾では、間違えたときに「恥ずかしい」と感じたり、周囲の目が気になったりする子どもも多いですが、「すらら」は1人で取り組めるため、そのようなストレスがありません。
間違えたとしても、自分のペースで何度でもやり直せるため、失敗を恐れずにチャレンジできます。
これにより、「学ぶことが楽しい」と感じるきっかけが増え、自然と学習意欲が高まるのが「すらら」の魅力です。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
「すらら」は、子どもが楽しく続けられるようにゲーム感覚の要素を取り入れた学習設計になっています。
単調な問題演習ではなく、アニメキャラクターがナビゲートしたり、クイズ形式で出題されたりすることで、飽きずに学習を続けられる工夫がされています。
これにより、集中力が続きにくい子どもでも「もうちょっとやってみよう」という気持ちになりやすくなっています。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
「すらら」では、アニメキャラクターがナビゲーションをしてくれるため、まるでゲームをしているかのような感覚で学習を進められます。
例えば、問題を解くとポイントがもらえたり、正解するとキャラクターが褒めてくれたりするため、モチベーションが自然と上がります。
また、クイズ形式で出題されるため、「次の問題にチャレンジしたい」という前向きな気持ちを引き出してくれます。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもは、「すぐに結果が出る」「すぐにフィードバックがある」とやる気が継続しやすい傾向があります。
「すらら」では、問題を解くとすぐに結果が表示され、正解すれば「よくできたね!」とキャラクターが褒めてくれるため、成功体験を積みやすくなっています。
また、スモールステップで達成感を積み重ねていくことで、自信につながりやすいのも特徴です。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
「すらら」には、専門の「すららコーチ」がついているため、親がすべてをサポートする必要がありません。
特に発達障害や学習障害のある子どもの学習サポートは、親にとって大きな負担になることがありますが、「すららコーチ」がいることで、その負担が大きく軽減されます。
コーチが学習の進捗を管理し、適切なアドバイスをしてくれるため、親子ともに安心して学習を進めることができます。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
「すららコーチ」は、ADHDやASD(自閉スペクトラム症)、学習障害などの特性を理解した対応をしてくれます。
例えば、ADHDタイプの子どもには「短時間で集中して取り組む方法」、ASDタイプの子どもには「ルーティンを決めて毎日続ける方法」など、子どもの個性に合わせたアドバイスをしてくれます。
これにより、無理なく自分に合ったペースで学習を進められます。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
「すららコーチ」は、AIが分析したデータをもとに、子どもに合った学習スケジュールを立ててくれます。
また、子どもがつまずいたポイントをコーチが把握し、どうすれば理解できるようになるかを丁寧にアドバイスしてくれます。
このため、「どこがわからないのかわからない」といった状態に陥ることがなく、スムーズに学習を進めることが可能です。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
「すらら」は完全オンライン型の教材なので、通塾や送り迎えの必要がなく、タブレット1台あれば自宅で完結できるのが大きな魅力です。
これにより、親の負担が減るだけでなく、子どもが自分のペースで自由に学習できる環境が整います。
また、体調やメンタルの状態に左右されることなく、いつでもどこでも学習できるのが強みです。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
「すらら」はインターネット環境とタブレットがあればすぐに始められるため、特別な準備が必要ありません。
また、オンライン教材なので教材の管理や保管場所の確保も不要で、常に最新の学習コンテンツが提供されます。
これにより、親が教材を管理したり、教科書を揃えたりする手間が省けるため、親の負担が大きく軽減されます。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
不登校や体調不良で学校に通えない期間でも、「すらら」なら家庭で無理なく学習を続けることができます。
AIが自動で学習スケジュールを組み立ててくれるため、学校の授業進度に左右されることなく、自分のペースで学習を進められます。
これにより、長期間学校を休んでしまった場合でも、学習の「穴」を作ることなく、自信を取り戻すことができます。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
「すらら」は、学習効果やサポート体制に定評がある一方で、「合わなかった」「思ったほど効果がなかった」と感じて解約や退会を検討するケースもあります。
ただし、「解約」と「退会」はそれぞれ意味が異なり、手続き方法も異なるため、違いを理解したうえで進める必要があります。
ここでは、すららの「解約」と「退会」の具体的な違いや手続きのポイントについて詳しく説明します。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
「すらら」では、「解約」と「退会」は別々の手続きとなっており、それぞれ意味や影響が異なります。
単に「利用をやめたい」だけなのか、「アカウント情報も完全に削除したい」のかを明確にする必要があります。
すららの解約は「利用を停止すること」。
毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
「解約」とは、すららのサービス利用を停止する手続きのことです。
解約手続きを行うことで、毎月の利用料の支払いが停止されます。
ただし、解約後も一定期間はアカウントや学習データが保持されるため、再開する場合にはすぐに学習を再開できるというメリットがあります。
特に「しばらく休みたい」「様子を見てから再開したい」といった場合は、解約を選ぶ方が適しています。
解約手続きを完了した場合、契約期間が終了するまではサービスを利用できることが多いため、最終利用日を確認しておくと安心です。
すららの退会は「すららの会員そのものをやめること」。
データも消える。
「退会」とは、すららのアカウントそのものを完全に削除する手続きです。
退会を行うと、これまでの学習データや成績、個人情報がすべて削除されるため、再開する場合は新規登録が必要になります。
解約とは異なり、データが完全に消えてしまうため、「もう絶対に使わない」「データを残したくない」といった場合に適した手続きです。
また、退会後は同じアカウントを復活させることができないため、注意が必要です。
特に、子どもが「またやりたい」と言い出す可能性がある場合は、すぐに退会せずに「解約」にしておく方が柔軟に対応できます。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
| 【すららコール】
0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
「すらら」の解約は、電話でのみ受け付けています。
メールやWEBからの解約手続きには対応していないため、必ず「すららコール」(サポートセンター)に電話をする必要があります。
サポートセンターは平日・土日ともに対応しているため、都合のよい時間に連絡できます。
ただし、受付時間外は対応していないため、事前に営業時間を確認しておくとスムーズです。
また、電話が混み合っている場合もあるため、余裕を持って連絡することをおすすめします。
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
「すらら」は、解約手続きをメールやWEBから行うことができません。
そのため、必ず電話での手続きが必要となります。
WEBから「解約フォーム」が存在しないため、間違ってお問い合わせフォームから解約依頼を送っても受理されないため注意が必要です。
また、電話連絡のみの対応となっている理由は、本人確認や意思確認を確実に行うためと考えられます。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
解約手続きの際には、本人確認が必要になります。
すららコールに電話をした際に、登録者の氏名やID、登録している電話番号などをオペレーターに伝える必要があります。
これにより、第三者が勝手に解約を行うことを防ぐ仕組みとなっています。
本人確認がスムーズに進むように、事前に登録情報を確認しておくと手続きがスピーディーに進みます。
また、未成年の利用者の場合は、保護者が手続きを行うことになるため、保護者名義での確認になるケースもあります。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
解約の手続きが完了したら、解約希望日をオペレーターに伝えます。
「すぐに解約したい」「契約満了日まで使いたい」などの希望を明確に伝えることで、スムーズに解約手続きを進めることができます。
ただし、「すらら」は日割り計算に対応していないため、解約日によっては1か月分の利用料が発生する可能性があります。
そのため、月末に解約した方が無駄なく利用できるケースが多いため、解約希望日は慎重に決めることをおすすめします。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
解約手続きを完了した後、さらに退会を希望する場合は別途「退会依頼」を行う必要があります。
解約と退会は異なるため、単に「利用をやめたい」場合は解約のみで問題ありませんが、「データを完全に削除したい」「アカウント情報を消去したい」場合には退会手続きが必要になります。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
解約手続きの際に、オペレーターに「退会も希望する」と伝えれば、解約と同時に退会手続きも進めてもらえます。
退会を行うと、これまでの学習データや成績、個人情報がすべて削除されるため、再開したい場合には新たにアカウントを作成する必要があります。
解約のみであれば、データは保持されるため、必要に応じて再開が可能です。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
「すらら」は、解約だけでも料金の支払いが停止されるため、退会をしなくても問題はありません。
データが残っている状態であれば、いつでも再開が可能です。
「とりあえず解約だけしておきたい」「また使う可能性がある」という場合は、退会せずに解約のみを選択することで、必要に応じて再開できる柔軟性があります。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
「すらら」は、家庭用タブレット教材として人気がありますが、「効果的な使い方がわからない」「子どもが続けられない」といった声もあります。
すららはAIによる個別最適化と、プロのコーチによるサポートが特徴のため、正しい使い方を実践すれば効果が大きく高まります。
ここでは、特に小学生が「すらら」を最大限に活用するための効果的な使い方を紹介します。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生の場合、集中力やモチベーションが持続しにくいため、短時間で集中して取り組める環境を作ることが重要です。
また、「できた!」という達成感をこまめに味わわせることで、継続しやすくなります。
親のサポートや声かけも重要なポイントとなります。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
「すらら」は短時間でも集中して取り組むことで、効果的な学習が可能です。
1回あたりの学習時間は20〜30分を目安にすると、子どもが飽きずに集中しやすくなります。
毎日少しずつ続けることで、学習が習慣化し、理解度も着実に高まります。
特に、朝や夕方など決まった時間に取り組むことで、生活リズムが整い、勉強習慣が自然と身につきます。
長時間取り組むよりも、短時間で集中して行う方が効率が良いため、「短く・頻繁に」を意識することがポイントです。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
「すらら」では、1ユニットや1セクションが終わるごとに「できた!」という達成感を感じられるような仕組みを取り入れると、子どものモチベーションが持続しやすくなります。
例えば、「1ユニット終わったらシールを貼る」「○○回正解できたら好きなおやつをあげる」など、視覚的・感覚的に成果を感じさせることで、次への意欲が高まります。
また、「よく頑張ったね」「できるようになったね」と声をかけることで、子ども自身が「自分はできる」と感じ、自信につながります。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
特に低学年の場合、親が一緒に取り組むことで、子どもが「勉強=楽しいこと」と感じやすくなります。
例えば、「今日は一緒に国語をやってみよう!」と声をかけたり、問題を解いたときに「すごいね!」とリアクションをしたりすることで、子どもは「勉強が楽しい」と感じやすくなります。
親が「勉強しなさい」と言うよりも、「一緒にやろう」と誘うことで、自然と勉強への抵抗感が薄れていきます。
また、親が一緒にいることで、間違えても「大丈夫だよ」と安心感を与えることができ、チャレンジへの意欲も高まります。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
「すらら」はAIが子どもの学習データを分析し、苦手な単元や理解が不十分な分野を特定してくれます。
好きな科目や得意な科目ばかりをやってしまうと、学習が偏ってしまうため、AI診断を活用して「苦手克服」にフォーカスすることが重要です。
例えば、国語の読解が苦手な場合、すららのAIが自動的に読解問題を強化してくれるため、効率的に克服することができます。
苦手を克服することで「できた!」という達成感が生まれ、自信を持って次の学習に取り組めるようになります。
また、親が「ここまでできたね」「成長したね」と声をかけることで、モチベーションも持続しやすくなります。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生の場合、勉強への取り組み方やモチベーションが小学生とは異なります。
部活や課外活動との両立、定期テスト対策、受験勉強への意識が高まる時期だからこそ、「すらら」を効果的に使うことで、限られた時間の中で最大限の成果を得ることが可能です。
AIが自動で学習計画を立ててくれるため、自分に合ったペースで効率よく進められるのが「すらら」の強みです。
ここでは、中学生に特化した「すらら」の効果的な使い方を詳しく紹介します。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
「すらら」には、単元ごとにまとめテストが用意されているため、定期テスト対策に直結した学習が可能です。
テスト範囲を事前に把握し、範囲に合わせた学習計画を立てることで、無駄のない勉強ができます。
AIが学習データを分析し、どの単元を優先してやるべきかを提示してくれるため、自分で「何をやるべきか」を迷うことがありません。
また、定期テスト直前には「すらら」のまとめテストを活用して総仕上げをすることで、理解度を確認し、得点力を高めることができます。
定期テストでの高得点は内申点アップにつながるため、早い段階から計画的に取り組むことが重要です。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
中学生は部活や課外活動で忙しいため、学習時間を確保するのが難しいケースがあります。
そのため、夜寝る前の30分~1時間を「すらら」の学習時間としてルーティン化することで、無理なく勉強習慣を作ることができます。
例えば、「部活から帰ってきたらシャワーを浴びて、夜9時から30分間すららをやる」と決めてしまうと、自然と学習リズムが定着します。
寝る前に学習した内容は記憶に定着しやすいため、効果的に知識を吸収できるのもポイントです。
また、疲れている日は「短めにしてもOK」と柔軟に対応することで、無理なく続けることができます。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
「すらら」には、プロのコーチによる学習サポートがついています。
すららコーチは、AIが分析したデータをもとに、学習計画や理解度のフォローをしてくれるため、「何をやるべきかわからない」「この単元が苦手だけど、どう克服すればいいかわからない」といった悩みを解消してくれます。
例えば、「数学の方程式が苦手」と相談すれば、すららコーチが「この単元から取り組んでみよう」とアドバイスをしてくれるため、的確なサポートを受けることができます。
また、モチベーションが低下しているときには「ここまで頑張っているから大丈夫だよ」と励ましてくれるため、精神的なサポートも得られます。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
「すらら」は無学年学習に対応しているため、予習と復習のどちらにも効果的に活用できます。
特に英語や数学は、文法や公式を事前に理解しておくことで、学校の授業がわかりやすくなります。
例えば、学校の授業で新しい単元に入る前に「すらら」で予習しておけば、「授業で先生の説明がスムーズに入ってくる」「問題が解きやすくなる」といった効果があります。
また、授業で理解できなかった部分は「すらら」で復習することで、苦手をそのままにせず、確実に克服できます。
復習を繰り返すことで理解が定着し、応用問題にも対応しやすくなります。
予習と復習をバランスよく行うことで、授業理解度が深まり、成績アップにつながります。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると、学習内容が一気に難しくなり、勉強の量も増えるため、効率的に学習を進めることが重要になります。
学校の授業についていけない、模試の成績が伸びないといった悩みを抱える高校生は少なくありません。
「すらら」は、AIによる個別最適化と無学年学習を活用することで、高校生でも自分のペースに合わせた効果的な学習が可能です。
基礎から応用までカバーしているため、苦手克服から受験対策まで幅広く対応できるのが「すらら」の強みです。
ここでは、高校生に特化した「すらら」の効果的な使い方を紹介します。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校生の学習で重要なのは、「苦手克服」と「得意分野の強化」をバランスよく進めることです。
「すらら」では、AIが学習データをもとに苦手な単元を自動で抽出してくれるため、理解不足な部分を集中的に学習できます。
例えば、数学の方程式が苦手な場合、AIが基礎から復習するカリキュラムを自動で提示してくれるため、「わからないまま進む」ということがなくなります。
一方、得意な分野については、応用問題や発展問題に挑戦することで、さらにレベルアップを図ることができます。
このように、「苦手の克服」と「得意の強化」を並行して進めることで、全体的な学力アップが可能になります。
また、苦手を克服することで自信がつき、他の教科や単元へのモチベーションも高まります。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
学校の授業が自分に合わないと感じる高校生にとって、「すらら」は効果的な学習手段となります。
学校の授業はクラス全員のペースで進むため、「理解できないまま授業が進んでしまう」「授業が簡単すぎて退屈」といったギャップを感じることがあります。
「すらら」では、自分の理解度に合わせてペースを調整できるため、無理なく学習を進めることが可能です。
理解が浅い部分は何度でも戻って復習でき、得意な分野はどんどん先に進めるため、効率的な学習ができます。
例えば、英語の文法が苦手な場合は「すらら」で基礎から復習しつつ、得意な数学は発展問題に挑戦する、といった柔軟な学習が可能です。
このように、「すらら」を使うことで、学校の授業に縛られることなく、自分に合った学習スタイルを確立できます。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
高校生にとって重要なのが、模試や共通テストへの対応力を高めることです。
「すらら」は基礎学力の定着に優れているため、模試や共通テストでの得点力アップに直結します。
AIが理解度を細かく分析し、基礎が不十分な単元を自動でピックアップしてくれるため、効率よく基礎力を固めることが可能です。
また、過去問や実践問題も用意されているため、実戦力を磨くこともできます。
例えば、「数学の関数が苦手」という場合、AIが自動で「関数」の単元を重点的に出題してくれるため、自然と苦手を克服できます。
また、模試や共通テスト前には「すらら」のまとめテストを活用して仕上げを行うことで、テスト本番に向けた準備が万全になります。
基礎力を徹底的に固めることで、応用問題や初見の問題にも対応できる力が自然と身につきます。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
「すらら」では、学習時間や達成度がグラフで可視化されるため、自分の学習状況を一目で確認できます。
高校生になると勉強量が増えるため、「どれだけ勉強したか」「どの単元を重点的にやるべきか」を明確に把握することが重要です。
「すらら」では、日々の学習時間や正解率、苦手分野の進捗などがデータとして記録され、グラフやチャートで表示されるため、「自分がどれだけ頑張っているか」「どこを改善すべきか」が一目でわかります。
また、学習時間や達成度が視覚化されることで、モチベーションが維持しやすくなる効果もあります。
「昨日よりも10分多く勉強できた」「正解率が80%を超えた」など、小さな成功体験が積み重なることで、自然とやる気がアップします。
学習時間や成果が見えることで、自己管理がしやすくなり、受験勉強への意欲も高まります。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校の子どもにとって、学習への不安や孤立感は大きな問題となります。
学校に通えないことで学習の遅れや生活リズムの乱れが生じ、自信を失ってしまうケースも少なくありません。
「すらら」は、自宅で自分のペースに合わせて学習を進められるため、不登校の子どもにとって非常に有効なサポートツールとなります。
AIが学習状況を自動で分析し、理解度に応じたカリキュラムを提示してくれるため、無理なく学習を続けられるのが「すらら」の強みです。
また、プロのコーチによるサポートが受けられるため、孤立感を和らげ、安心して学習に取り組める環境が整っています。
ここでは、不登校の子どもに特化した「すらら」の効果的な使い方を紹介します。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校になると、生活リズムが乱れてしまうことがよくあります。
朝起きる時間がバラバラになったり、夜更かしをしたりすることで、昼夜逆転が起こるケースも少なくありません。
「すらら」を活用することで、規則正しい生活リズムを作ることが可能です。
例えば、「朝8時に起きたら、30分間すららで学習する→10分休憩→また30分間学習する」といった「ミニ時間割」を作ることで、1日の流れを整えることができます。
毎日決まった時間に「すらら」を取り入れることで、生活にリズムが生まれ、心身の安定につながります。
また、時間割を親と一緒に決めることで、親子のコミュニケーションも増え、安心感が得られます。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
学校に行けなくなる理由のひとつに「集団での学習が苦手」「周囲の目が気になる」といった心理的なプレッシャーがあります。
「すらら」は、タブレット1台があれば自宅で一人で学習できるため、周囲の目を気にせず自分のペースで取り組むことができます。
学校の授業は全員が同じペースで進むため、理解が追いつかない場合に「焦り」や「劣等感」を感じやすくなりますが、「すらら」では理解できなかった単元に戻ったり、必要に応じてAIが最適なカリキュラムを提示してくれるため、無理なく学習を進められます。
人と比べる必要がないため、自己肯定感を損なわずに安心して学習できる環境が整っています。
また、「わからないまま進むことがない」という安心感があることで、学習への抵抗感がなくなりやすくなります。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
不登校になると、どうしても「自分はできない」「みんなと違う」という自己否定の感情が強くなりがちです。
「すらら」には、問題を解いたときに「正解!」と画面に表示されたり、キャラクターが「よくできたね!」と声をかけてくれる「ほめ機能」が備わっています。
例えば、苦手な単元をクリアしたときに「すごいね!がんばったね!」とキャラクターが励ましてくれることで、成功体験を積み重ねることができます。
これにより、「できた!」という達成感が得られ、自信が回復しやすくなります。
また、親が「すごいね!ここまでできたんだね!」と声をかけることで、さらに子どもの自己肯定感が高まります。
「すらら」で成功体験を増やすことで、「自分にもできる」という自信が芽生え、他の場面でも前向きな行動が取れるようになります。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校になると、家にいる時間が長くなることで「親子だけの閉じた関係」になりがちです。
親は子どもを支えようとする一方で、子どもは「親に迷惑をかけている」と感じてしまうケースもあります。
「すらら」のコーチングサポートは、第三者の立場から学習や精神面のアドバイスをしてくれるため、親子関係がギクシャクしにくくなります。
例えば、「どうしても数学が理解できない」といった場合に、親が教えると「親の言い方が気に入らない」と反発してしまうことがありますが、「すららコーチ」は冷静に子どもの理解度を把握し、「この単元をやってみよう」「ここは少しずつ慣れれば大丈夫だよ」と具体的なアドバイスをしてくれます。
また、勉強だけでなく「勉強のやる気が出ない」「学校に行きたくない」といった相談にも対応してくれるため、気持ちの負担が和らぎやすくなります。
「すららコーチ」は、学習サポートとメンタルケアを兼ね備えているため、親子関係を良好に保ちながら安心して学習を進めることが可能です。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです/アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました/先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…/もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…/サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です/進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…/もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります/特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照:会社概要(すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
「すらら」は効果的な学習サポートが特徴の家庭用タブレット教材ですが、ネット上では「うざい」という声が見られることもあります。
また、発達障害対応コースや不登校の子どもへのサポート、キャンペーンコードの使用方法などについても疑問を持っている方が多いようです。
ここでは、「すらら」に関するよくある質問について詳しく解説します。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すらら」に関して「うざい」という口コミがある理由はいくつか考えられます。
ひとつは、すららコーチやサポートからの連絡が「しつこい」と感じるケースです。
定期的な進捗確認やアドバイスの連絡が頻繁に届くため、自分のペースで進めたいと考えている人にとっては「干渉されている」と感じることがあるようです。
また、学習を進めている際にキャラクターのナビゲーションや解説が「くどい」と感じることもあるようです。
特に思春期の子どもにとっては、キャラクターが幼く見えることで「子どもっぽい」と思われてしまうケースもあるようです。
しかし、コーチからのアドバイスやキャラクターの存在は、学習モチベーションを高める目的で設計されているため、合わないと感じた場合はサポートの頻度を調整するなどの対応も可能です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららの発達障害対応コースは、特性に合わせた無学年方式の学習スタイルが特徴です。
発達障害の子どもに対応したカリキュラムが組まれており、学年にとらわれずに理解度に応じて学習を進められるため、負担を感じにくくなっています。
料金プランは通常のすららと基本的には同じで、3教科コース(国語・数学・英語)が月額約8,800円(税込)、5教科コース(国語・数学・英語・理科・社会)が月額約10,978円(税込)となっています。
また、AIによる個別最適化とすららコーチによるサポートが含まれているため、学習の進捗に応じて柔軟に対応してもらえるのが特徴です。
さらに、発達障害の子どもに特化したサポート体制も充実しているため、困ったときにはコーチに相談することが可能です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
「すらら」は文部科学省が推奨しているオンライン教材であり、不登校の子どもが「すらら」を活用して学習を続けている場合、学校によっては出席扱いとして認定されるケースがあります。
具体的には、学校がすららを学習教材として正式に認めている場合に限られます。
そのため、事前に学校や教育委員会に「すららでの学習が出席扱いになるかどうか」を確認しておくと安心です。
出席扱いになる条件としては、学校側に学習状況の報告を行い、成果や理解度を確認してもらう必要があります。
また、すららコーチが作成した学習計画や進捗状況を学校に提示することで、出席扱いになる可能性が高くなります。
不登校の子どもでも「すらら」を通じてしっかり学習を続けることで、進級や卒業に必要な単位を取得することが可能になります。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
「すらら」では、定期的にキャンペーンが行われており、新規入会や期間限定でお得に利用できるキャンペーンコードが発行されることがあります。
キャンペーンコードの使用方法はシンプルで、新規登録時に専用の入力欄にコードを入力するだけで割引が適用されます。
また、既存のユーザー向けに「家族割」や「友達紹介キャンペーン」なども実施されている場合があります。
キャンペーンコードの有効期限や適用条件はそれぞれ異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、一部のキャンペーンコードは他の割引と併用できない場合があるため、公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
「すらら」の退会方法は、まず「すららコール」(サポートセンター)に電話をして手続きを行います。
メールやWEBからの退会には対応していないため、必ず電話での連絡が必要です。
退会手続きを行う際には、登録者名や電話番号、アカウントIDなどの本人確認情報を伝える必要があります。
また、退会と解約は意味が異なり、「退会」を行うとこれまでの学習データや成績がすべて削除されるため、再開したい場合は新規登録が必要になります。
「解約」の場合は、料金の支払いが停止されるだけでデータは保持されるため、再開を考えている場合は「退会」ではなく「解約」を選ぶ方が柔軟に対応できます。
退会を行った場合、データが完全に消えるため「もう絶対に使わない」と判断した場合に限って退会を行うのが望ましいです。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
「すらら」の料金体系は非常にシンプルで、基本的には入会金と月額受講料のみで利用が可能です。
入会金は初回のみ発生し、以降は月額の受講料を支払うことで継続して利用できます。
入会金は通常10,000円(税込)程度となっており、時期によってはキャンペーンで入会金が割引または無料になることもあります。
受講料は、3教科(国語・数学・英語)コースが月額8,800円(税込)、5教科(国語・数学・理科・社会・英語)コースが月額10,978円(税込)です。
これ以外に追加で料金がかかるケースとしては、タブレット端末を持っていない場合に新たに購入する費用や、インターネット接続費用が挙げられます。
また、教材や問題集などの追加購入は必要なく、すららに用意されているデジタル教材だけで学習が完結するため、コストパフォーマンスは高いといえます。
一度契約すれば追加料金なしでカリキュラムや教材がアップデートされるため、長期的に見てもコスパの良い学習環境が整っています。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
「すらら」では、1つの契約で兄弟や姉妹が一緒に利用できるという大きなメリットがあります。
通常、オンライン教材は1人につき1つの契約が必要ですが、「すらら」では追加料金なしで兄弟や姉妹が同じアカウントを使用することが可能です。
例えば、小学生の兄と中学生の妹がいる場合、1つのアカウントでそれぞれの学年や理解度に応じたカリキュラムに取り組むことができます。
また、兄弟で異なる教科を学習したい場合でも、それぞれの進捗状況や理解度に合わせてAIが個別に最適なカリキュラムを提示してくれるため、効率的に学習を進めることができます。
さらに、兄弟で一緒に学習することで「一緒に頑張ろう」という意識が生まれ、相乗効果によって学習意欲が高まることも期待できます。
ただし、同時にログインできるのは1人のみとなるため、別々の時間帯で利用する必要があります。
すららの小学生コースには英語はありますか?
「すらら」の小学生コースには、英語のカリキュラムも含まれています。
小学生コースの英語では、単なる単語や文法の暗記ではなく、リスニングやスピーキングを重視した「実践型」の学習ができるのが特徴です。
例えば、ネイティブの発音を聞きながら英語に触れることで、自然と英語のリズムやイントネーションが身につくように設計されています。
また、英単語やフレーズを繰り返し聞くことで、発音や意味を感覚的に覚えることができるため、「英語に苦手意識を持たない」状態を目指します。
さらに、すららでは「発音チェック機能」や「ロールプレイング形式」の問題も用意されており、インプットだけでなくアウトプットにも重点を置いたカリキュラムが組まれています。
AIが子どもの理解度や発音の正確性を自動で分析し、理解不足な部分を的確に補強してくれるため、英語に対する自信がつきやすくなります。
また、小学校で必修化された英語教育に対応しており、授業の予習や復習としても効果的に活用できます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
「すらら」では、プロの「すららコーチ」が学習計画の作成から日々の学習サポートまで幅広く対応してくれます。
すららコーチはAIが分析した学習データをもとに、子どもの理解度や苦手分野を把握し、最適な学習スケジュールを提案してくれます。
例えば、「数学の方程式が苦手だけど、図形は得意」といった場合、すららコーチが「まずは方程式を重点的に復習してから、図形の応用問題に挑戦しよう」といったアドバイスをしてくれます。
また、子どもが学習に対してモチベーションが下がった場合にも、「ここまでできたから、あともう少し頑張ろう」「今日は短めにしてみよう」といった精神的なサポートをしてくれるため、継続しやすくなります。
さらに、保護者に対しても子どもの学習状況を報告し、家庭でのサポート方法をアドバイスしてくれるため、家庭全体で学習に取り組むことができます。
すららコーチは、単なる学習指導にとどまらず、メンタルサポートや家庭との橋渡し役としての役割も担っているため、子どもが孤独を感じずに安心して学習を続けることができるのが特徴です。
また、不登校や発達障害に特化したコーチも在籍しており、特性に応じたサポートを受けることが可能です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
すららは「うざい」と感じる口コミが一部にあるものの、多くのユーザーは効果的な学習サポートを受けていると評価しています。
料金面ではコースやサポート内容によって異なりますが、無学年方式のため自分のペースで学習できる点が魅力です。
悪い噂については、実際の体験談を確認すると、教材の使い方やサポート体制に関する不満が見られることもあります。
ただし、総合的には学力向上につながったという声も多く、タブレット教材としてのメリットを感じているユーザーも多いようです。
自分に合った学習スタイルかどうかをしっかり検討することが大切です。